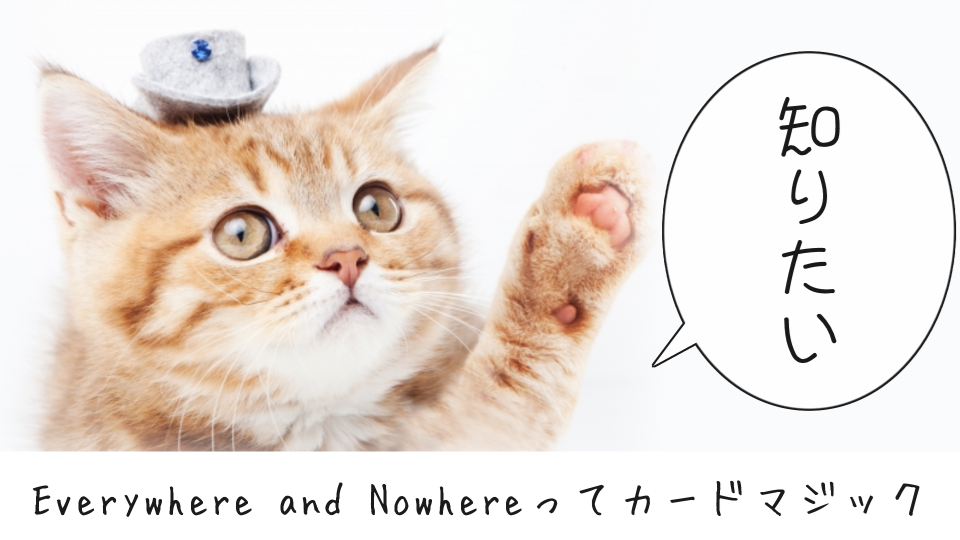まえおき
最近、ヘルダー・ギマレスの「Everywhere and Nowhere」を読んで、「あ、こんなアプローチもあるのか!」とちょっと感心しました。
- チェンジを多用するので難しい
- デュプリケイトを使う
- 本質は「おしゃべり」にあること
- サロン向けのトリックであること(クロースアップが一般的じゃなかった時代なので、ハンドリングもクロース向けではない)
Everywhere and Nowhereの現象
「Everywhere and Nowhere(どこにでもあって、どこにもない)」は、カードマジックのクラシックな作品のひとつです。流れをざっくり説明すると、こんな感じになります。
-
演者は一組のトランプを使い、観客に1枚カードを選んで覚えてもらい、デックに戻してもらいます。
-
「ちょっとした方法を使えば、すぐにカードを当てられるんですよ」と言って1枚取り出すのですが……外れ。テーブルに置いておきます。
-
気を取り直して2枚目を取り出すも、また外れ。
-
3枚目も外れ。結局、3枚とも間違ったカードがテーブルに並びます。
-
「これではさすがに申し訳ないので、違うやり方を試しましょう」と言って、観客にこの“外れカード”3枚から1枚を選んでもらいます。すると――そのカードが観客の選んだカードに変わってしまうのです。
-
驚いている観客に「では残りの2枚のどちらか…」と選んでもらうと、そのカードも観客のカードに変化。
-
最後に残った1枚も同じように観客のカードに変わります。つまり、テーブルの3枚すべてが観客のカードになってしまうのです。
-
ここで観客は当然「同じカードが何枚もあるんじゃないの?」と疑いを持ちます。ところが――最後には3枚とも元の“外れカード”に戻ってしまう。
-
さらにデックを広げて調べても、観客のカードはどこにも見つからない。つまりタイトル通り、“どこにでもあるし、どこにもない”状態で幕を閉じるのです。
ちょっと調べたEverywhere and Nowhereのメモ
The Art of Magic
Johann Nepomuk Hofzinser — Everywhere and Nowhere
- ダウンズによるホフジンザー手順の解説。
- 台詞も一言一句そのまま収録との触れ込み。
- デュプリケイト2枚使用。
- 演出:数学的に当たる確率を高めると言いながら3度失敗。
→ 「計算ミス」を口実に、観客(特に女性)の視線の力を借りて外れカードが変化していく。
T. Nelson Downs — Everywhere and Nowhere: New Method
- 演出はホフジンザー版と同じ。
- ブラックアート使用。
- デックを40枚程度に減らすとやりやすいと注意あり。
- ヨーロッパでは「ピケ・デック」という32枚デックが普及しており、ホフジンザーもそれを使用していたので、ダウンズはそれ知らずに書いてる可能性がある。
- 準備物に「メモとペン」とあるが、実際には使われていない。
T. Nelson Downs — The General Card
- Everywhere and Nowhere と似た現象。
- ただし演出・手法が異なり、便宜的にこのタイトルを付けて紹介されている。

あそびの冒険1巻には『Art of Magic』に載っている「Everywhere and Nowhere」と「The General Card」の訳が載ってます。NEW METHODはないけど
Hofzinser’s Card Conjuring
Johann Nepomuk Hofzinser — Everywhere and Nowhere (First Method)
- デュプリケイト2枚使用。
- ダウンズの『The Art of Magic』にある解説とほぼ同じ構成。
- 違いは「間違ったカードを出す」部分に特に理由づけがされておらず、説明的なストーリーは付けられていない点。
- 後半は「女性の視線には魔力がある」という流れで、外れカードが変化していく。
Johann Nepomuk Hofzinser — Everywhere and Nowhere (Second Method)
- デバイデッド・カード使用。
- 演出:序盤は観客に質問を重ね、心理学的に候補を絞り込んでいく流れ。
- 後半はやはり「女性の視線には魔力がある」としてカードが変化する。
Johann Nepomuk Hofzinser — Everywhere and Nowhere (Third Method)
- デュプリケイト + デバイデッド使用。
- 演出:序盤は質問をして心理学的にカードを絞り込み、後半では選ばれたカードがデックの中を縦横無尽に移動しているかのように見せる。

ダニ・ダオルティスの「The Mirage」を想像してもらえれば、それが一番近いと思う
Greater Magic
Paul Rosini — Everywhere and Nowhere
- デュプリケイト2枚使用。
- 特筆すべき変更点なし。
The Royal Road to Card Magic
不明 — Everywhere and Nowhere
- デュプリケイト2枚使用。
- グラスをカード立てとして使う。
- 『カードマジック事典』でホフジンザー版として紹介されているのはこの手順。
Expert Card Technique
不明(Lybrary.comではFrederick Braue作と記載あり) — Everywhere and Nowhere
- デュプリケイト2枚使用。
- 小道具:ウサギの足のお守り。
- 外れのカードとして、ハートA、ダイヤA、クラブAを使う。
- 失敗を繰り返した後、「ウサギの足の力」で催眠術のようにカードを観客のカードに変えて見せる。
Sonata
Juan Tamariz — The Hypnotic Power of the Jokers
- スライト主体の手順。
- Roberto Giobbi が絶賛した作品。
- 現象は「General Card」に近く、本流の Everywhere and Nowhere とはやや異なる。
Card College Vol.4
Roberto Giobbi — Everywhere and Nowhere
- デュプリケイト使用。
- 小道具:塩瓶。
- 「指を鳴らす → 上がる/下がる → 失敗」という演出。
- ホフジンザー・トップチェンジを「塩を払う動き」にカモフラージュしている。
Utopia
Dani DaOrtiz — I.E.N
- レギュラーデックのみ使用。
- 不思議さはデュプリケイトを使ったときの効果に迫る。
- 後半は「General Card」に展開。
- 演出テーマ:「恋をすると、どこにいてもその人に見える」。
Secret Language Vol.1
Helder Guimarães — Unexplained Understandable
- デュプリケイト3枚使用。ワイングラスを併用。
- これまでのデュプリケイトの使い方と大きく異なる発想。
- 演出は非常に哲学的で、表現しづらい独特の世界観を持つ。
Ultimate Secrets of Card Magic
Fred Kaps — The Three Jokers
- ジョーカーとワイングラスを使用。
- トップチェンジに依存していた部分を、観客に凝視されても通用する方法に置き換えた。
- 演出:選んだカードをトップやボトムから自在に取り出すと宣言 → 失敗 → 外れカードが観客のカードに変化する。