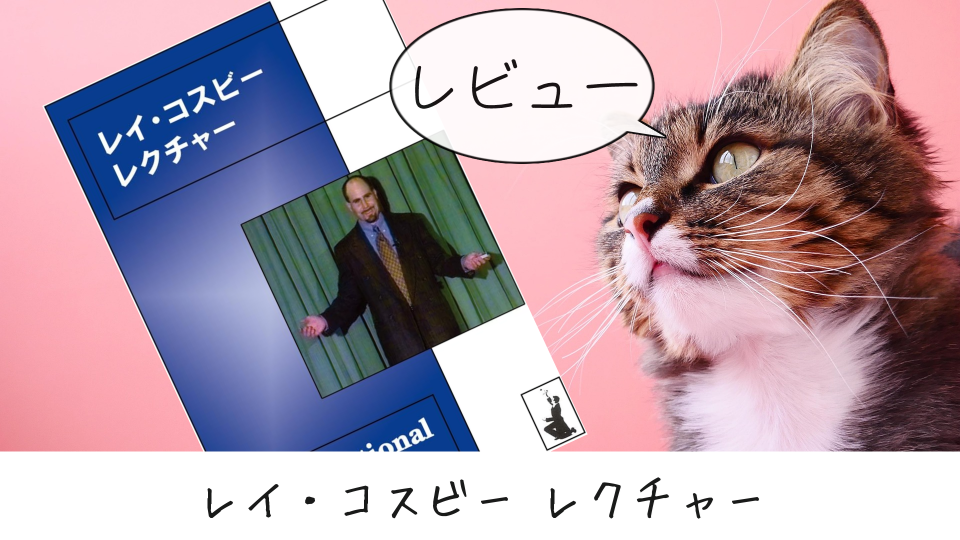Ray Kosby Lectureとは?
「レイズ・ライズ」が多分有名になった一番のきっかけだとわたしは思っている、レイ・コスビー(Ray Kosby)氏のレクチャーDVD。日本語字幕版がスクリプト・マヌーヴァ社から発売されています。
レイ・コスビー・レクチャー 日本語字幕版(Amazon)
レイ・コスビー・レクチャー(スクリプト・マヌーヴァ)
総評
収録作品はどれも難易度が高めで、マジシャンがマニア同士で見せるための~と言った印象が強いですが、他ではあまり見かけないような現象やアイディアもあって中々に興味深い。
このDVDに興味を持つ人は大体が「レイズライズ」目的だと思いますが、日本語だけあって理解しやすい。ただ、日本語だから日本人には分かりやすいということであって、全体を通して解説は必要最小限だと感じました。おそらくというか、以降の作品集でも解説がかなり淡白なのでレイは解説があまり得意ではないのでしょう。
「レイズライズが上手く出来ない、字幕があればコツとか分かるかもしれない」という目的であれば、多分得る物はないと思います。あと、ビジュアルなトリック以外に関しては、緊張しているのか、この頃はそもそも演じるのが苦手なのか、演技がかなり雑です。
「レイズライズ」をやってみたいという場合であれば、本作で良いと思いますが、レイズライズで使われている技法「アンビシャス・ライザー」を使ったトリックを知りたい・すでにある程度出来る場合であれば、氏のDVD『Impossible Card Magic』の方が良いです(いうてレイズライズを含めて4種類ですが)。英語版しかありませんけども。
というところを踏まえて、難易度が高くても風変わりなアイディアなんかを知りたい人、レイズライズに挑戦してみたいという人には面白いDVDです。
あ、あと基本的な技法は一切解説されていませんので注意ですね。ワンハンドパームくらいは出来て当然くらいの前提ですよ。
Impossible Card Magic – Volume 2 by Ray Kosby(Vanishing inc.)
個別の感想
ドレッシング・フォー・カラー・チェンジ
デックをすべて記憶するという体の演出でカード当てる。取り出した2枚のマークと数字が選んだカードを示しているというが間違ったカードが表れ、取り出した2枚のマークと数字が逆だったと言って場所を入れ替えると、間違ったカードが正しいものに変わる。
テンパっているのか、観客が理解出来ないまま進行してしまっているようで、実演は初心者みたいだったし、肝心のクライマックスのチェンジも失敗?といって差し支えないような状態だった。
カラーチェンジは何かしら別の現象にも使えそうでした。
ただ、複数枚パームしたままスプレッドしたりと進行するんですけども、流れ的にパームしたまますることで現象が綺麗になっているかといえば完全にNOで、その使い方だと大体の人は途中でパームトランスファーとかした方が楽になる上に綺麗ですね。
ヘルダー・ギマレスが、オープナーでパームしたままドリブルして1枚引いてもらってから~っていうトリックをしていましたけど(多分レッドミラー)、あれはちょっと無理することで次の動作がシームレスになって難しいことをするだけの価値がありましたけど、このドレッシングに関しては「得意だからそのままやった」以上の意味がないので、そのまま真似しない方が良いと思います。難易度が高い上に、観客の視線的にリスクが高く、結果起こり得るミスが実演でそのまま出てます。
カラーチェンジは面白いけど、トリック全体では微妙って感じです。
カラー・チェンジ
3枚の赤裏カードを振ると1枚ずつひっくり返る。再度同じことすると今度は3枚とも赤から青裏に変化し、デックもすべて青に変わる。
難易度的に中々しんどいトリック。DVD『Impossible Card Magic』にある「THE OTHER CHEEK」と根っこは同じだけど、こちらはバックのカラーチェンジとデックのカラーチェンジも含まれています。
THE OTHER CHEEKと比べると、メインのリバース(とチェンジ)は同じなものの、導入や処理など色々と変化しているので、気になる人は比較してみても良いかもしれない。
もう一度言うけど大分しんどい。
Impossible Card Magic – Volume 2 by Ray Kosby(Vanishing inc.)
スマッジ
カードケースを掃除機に見立てて、ハートの3を吸うと真ん中のピップスが取れてハートの2になり、取れたハートのAがケースから出てくる。
DVD『Impossible Card Magic』にも収録されているPicking Off the Pip現象。非常にユニーク。
都合上、箱からトランプを取り出すところから始まっていて、このトリックを演じてしまわないと一部のトリックを演じるのに支障をきたすので、手順に組み込む際には考慮が必要。演じてしまえばデックはレギュラー状態なので序盤にするのが無難。あと、箱の爪は切り取っておかないいけません。
「投げる」やり方は『Impossible Card Magic』には無かった気がします(観客からは見やすいけど、ちょっと無難しい準備)。
Impossible Card Magic – Volume 2 by Ray Kosby(Vanishing inc.)
チンカチンク
4枚が集合した後、一瞬で四隅に戻る。
現象はクリーンだけど、中々やってみようとは思わないかな。
最後のエキストラの処理は、便利だけどクリーンではないっていう感じで、細部に拘る人は避けそうな感じ。そこの元アイディアはアルフォンソ氏で、レイはこのレクチャーの間めっっっっちゃ緊張しているようなので、適切に演技できてない可能性もありそう。こうすることで4個だけフェアに~みたいなこと言っていましたし。
ブレイクが見えないように注意してます!って言いながらデックがぱっかーーんって開いたドリブルフォースしてる人みたいな感じかもしれない。
「Square One」っていう手順がDVD『Impossible Close-Up Magic』(名前が似てるけど、こっちはカード・マジックじゃなくてクロースアップ)に収録されているけど、PVを見る限りでは同じ。
Impossible Close Up Magic by Ray Kosby(Vanishing inc.)
コイン・スルー・ハンド
二段構成のコインスルーハンド。一段目は手の甲を下に向け、コインを下から上に向かって打ち込む感じに貫通。二段目はジャンボコインが手に握ったレギュラーとビジュアルに入れ替わる。
一般的なコインスルーハンドとはかなり異なった見た目。難易度的にはちょっとむずかし目かなってところ。
一段目は多少角度に弱めで、二段目に関しては1対1で観客が見下ろすような環境を推奨している。
PVを見る限り『Impossible Close-Up Magic』にも収録しているようで、「Silver And Bone」がおそらく同じっぽい。
また、ハンカチを使ったアイディアも収録されてて、もしかしたら「Twist The Threads」というトリックが同じor発展したトリックかもしれません。
コイン好きなら覚えておいて損はないんじゃないかな。
Impossible Close Up Magic by Ray Kosby(Vanishing inc.)
ジャック・イン・ザ・ボックス
ジャックをカードケースに乗せて叩くと中に入る。
びっくり箱(英語でJACK IN THE BOX)と引っ掛けたタイトルで、『Impossible Card Magic』の「JACK IN BOX」(theがないけど)と同じ。
ラリー・ジェニングスのトリックと大体同じということを言ってるけど、「アストロ・カード」のことなのかな。『The Collected Almanac』やその翻訳版『世界のクロースアップマジック』に収録されてます。
一瞬で終わる小ネタだけど、覚えておくとたまーに使いますよね。
そういえば、ビル・マローンがバリエーションを出してた気もします。
Impossible Card Magic – Volume 2 by Ray Kosby(Vanishing inc.)
Here I Go Again Volumes 1 – 3 by Bill Malone(Vanishing inc.)
アンイコール・バンド
大きな輪ゴムを千切ると小さい輪ゴムになり、最後には大中小3つの輪ゴムになる。
輪ゴムでやるプロフェッサーズ・ナイトメア。
3つのサイズ違いの輪ゴムがあれば即席でも演じれるし、多少複雑なところはあるけど(マジシャン側からすると)覚えてたら便利そうな手順。
終わった後に「輪ゴムは観客には見せずに仕舞いましょう」と言っていて、最初に見せたときとクライマックス後の、長さの状態的なことを心配しての発言なのかとは思うけど、色々説明が足りないなーと思いました。
バックワード・カード・トリック
エース・アセンブリ。4枚のジャックと3枚のXカードでマスターに集合した後に、逆戻り(バックファイア)する。
Allan Ackermanの「Reassembled Finale」を元にしたであろうトリック(Ackermanから許可をもらったとは言ってるけど、どの作品なのか言ってない)。
ただ、Reassembled FinaleよりもJ.C. Wagnerの「Dyslexic Queens」が近い・・・近いってよりも削ったっていう感じか。
他のトリックも同じだけど、ビジュアルなトリック以外を演じるのが苦手なようで、あれ?2倍速で見てたっけ?ってなるくらい、はじまったと思ったら終わってたって感じてしまう演じ方が気になった。
まぁ演じ方にあまり突っ込みすぎるのも駄目な気もするのでここまでにして、マスターパケットにしかXカードを配らないので、スローモーション・エーセスのような「各パケットからAやJが消失していく」パートを野暮ったい・カットしたい・面白く演じれない、って感じる人には合うかもしれません。
ただ「なんか速くやってしまうんだよな・・・」って自分で問題だと思ってる人は「Reassembled Finale」とか、ゆうきとも氏の「ピュア・セーセス」とかを演じた方が良いと思います。
ちなみに「Dyslexic Queens」は、どうあがいてもこの手順と同じくらいになると思います。
あとですが、この手順は「Jをデックから4枚取り出すとき」にシークレットムーブを行うので、ここで挙げた他のアセンブリと異なって、手順に組み込むときは前に演じるトリックは考える必要があります(まぁ、やろうと思えばなんとでも出来はするのですけど、レイは取り出すときに~っていうのを重視しているようなので)。
解説のときに、ユニットアディション、ジェニングスだったかな。と言ってるけども多分マーローのユニットアップジョグですね。
Reassembled Finale by Allan Ackerman(Lybrary.com)
The Las Vegas Card Expert and Every Move a Move by Allan Ackerman(Lybrary.com)
J.C. Wagner’s Commercial Magic Vol. 1(Penguin Magic)
オイル&ウォーター
三段構成のオイル&ウォーター。分離・分離・混合。
一段目は観客にちょっと手伝ってもらう。
二段目は交互に且つ裏表も混ぜるけど分離。
三段目では振ると交互に且つ裏表も混ざる。
枚数は8枚でエキストラなし。基本的な技法が出来れば演じれると思う、ただスムーズにやるにはちょっと練習が多めに必要。そんな感じの難易度。
『Impossible Card Magic』にも収録されているけど、三段目でこちらは、混ざる瞬間を片手で行うのに対し、『Impossible Card Magic』では両手を使った方法に変更されていました。当然片手の方が難しいです。
あと、手順に入る前に、スプレッドしたデックから観客と演者がそれぞれ4枚カードを引くと、観客は全部赤で演者は全部黒。というトリックを演じていますが、『Impossible Card Magic』ではこれは行われていません。準備が必要にはなるけど、O&Wの導入に良いトリックだと思いました(セットが要るので普段はあまり演じないとのことですが)。
Impossible Card Magic – Volume 2 by Ray Kosby(Vanishing inc.)
フォー・オブ・ア・カインド
観客が選んだ4枚のカードがフォー・オブ・ア・カインド。
デックを持って演者がスプレッドしていき、観客が指を指したカードをアップジョグしていく感じ。大分ごちゃごちゃした感じになるのでテーブルがあるならば演じることはなさそう。逆に立った状態で演じているならば使う機会はあるのかもしれない。
難易度的には難しい部類・・・だと思います。何度も技法を使うのと、どうしても見た目が汚くなるので最低限見た目を保ったままやることを考えたら。
『Impossible Card Magic』に収録されている「FREEDOM OF CHOICE」と同じ。
Impossible Card Magic – Volume 2 by Ray Kosby(Vanishing inc.)
レイズライズ
デックに突き出した状態でカードを差し込み、振るたびに上に少しずつ上っていくアンビシャスカード。
突き出したままやるアンビを「レイズ・ライズ現象」って呼ぶきっかけになった作品。使っている技法アンビシャス・ライザーは高難易度技法としてもよく挙がりますね。
ただここでは「アンビシャス・ライザー」って技法名は出てきていません。『Impossible Card Magic』では何度か出ていましたけど。
あ、トリック名が「レイズライズ」であの技法は「アンビシャス・ライザー」ですよ。
実は今回このDVDを見ていたのって、トニー・チャンのレクチャーでアンビシャス・ライザーをやっているのを見たんですけども、あれの作り方がレイと違うよなー・・・記憶違いかな?って思ったからなんですが、見たところレイは2つの方法を「両方使っているけど、解説では片方しか言ってない」で、トニー・チャンは「レイが解説してないけどさり気なくやっている方」を解説していたようでした。
よく間違っている人を見かけますが、この辺の食い違いのせいなのでしょうかね。どちらも状況によって使い分けるのが正しいのでしょうが、トニー・チャンがメインでやってる方法だけで「レイズライズ」をすると、準備のところがとてもぎこちなく見えるんですよね。泥棒がタンスを調べるときに上から開けてしまっているみたいな(上から開けると、下の段を見るときに1回閉めないといけない。下から開けるとそのまま上の段を開けれる。ってやつ)。
ちゃんと学べば無理な技法ではない・・・と思いたいですけど、子どもや女性や手の小さい人にはしんどい技法かもしれません。
そういえばレイズライズ現象も増えましたよね。エレベータームーブ、ソルタリーシフト、フォールン、ライオット、チェンズライザー、ライズ(ニコラス・ローレンス)、ルセロ(2種類見覚えある)の、The COON、G・U・G ELEVATOR、レイジー・ライズ、エスカレーターとか、ぱっと思い出せるのはこの辺ですけど。Xaviors Riseはノーカン。
Daniel Garcia Masterclass by Daniel Garcia(Vanishing inc.)
True Astonishments by Paul Harris(Vanishing inc.)
Nicholas Lawrence Live Lecture by Nicholas Lawrence
Paper Cuts – Volume 1 by Armando Lucero(Vanishing inc.)
Shinanigens by Shin Lim(Vanishing inc.)
Lazy Rise by Chris Mayhew(Vanishing inc.)
Escalator by Gaetan Bloom(Vanishing inc.)