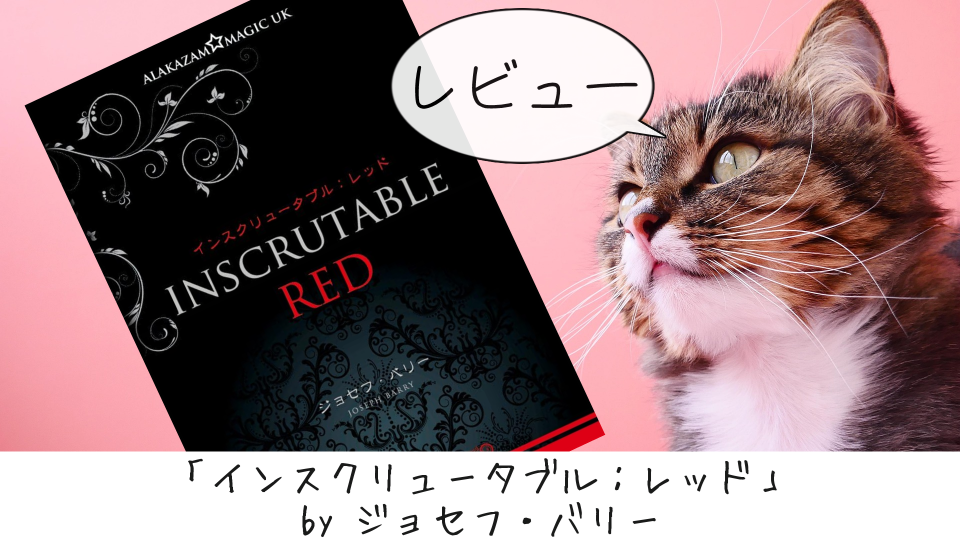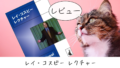INSCRUTABLE by Joseph Barry
2013年に発売されたジョセフ・バリーの2枚組DVDを、日本語翻訳して1巻と2巻に分けて発売したものの1巻「レッド」のレビュー。
ちなみに2巻(元は1巻のDisc2は「ブルー」、その後発売されたインスクリュータブル2は「グリーン」の名前で日本語版が発売された)

なので「レッド」とかタイトルに色がついてる時点で日本語版確定
英語版を買った直後に発売したので長らく放置、セールで買ったものの見ずに大分長い間放置していた。
インスクリュータブル:レッド ジョセフ・バリー(スクリプト・マヌーヴァ)
*Fantia・Creatiaから都合の悪い部分はカットしています
総評的な
カラーチェンジのようなビジュアルな見た目のトリックは少ないが、マジシャンが見ても不思議なカード当ての類が多め。2013年当時はスペインのマジックなんかが人気になった後、かなり広まった感があったと記憶している。スペイン風のマジックに近い傾向の作品が多い。
タネ自体はセルワのものも多く、8割位は不器用でも出来るもの。ということを語って入るのだけど、サイコロジカル・フォースやクラシック・フォースのような、シュアファイアじゃない手法も数多く使うので気軽にネタを増やせるようなものではないけど、そういった手法に抵抗のない人にはとてもよい刺激になる作品集だと思います。
個別に
レインマン
2段からなる記憶術トリック。
ちなみにタイトルは映画レインマンから。
2デックを使い、観客に両方混ぜてもらいスタート。2段目はどちらかと言えば予言になる。
メインで使うデックを選んでもらったら、残りのデックは答えや予言の提示に使う。1デックでも出来なくはないけれども(メモ紙使うみたいな方法で)、2デックあるからこそ出来るサトルティも構造に入っているし、説得力を強くするのにも貢献してるので尊重していきたい。
演出やコツなんかについてもしっかり話してるので必聴。ジョセフの言っている「テクニックを使わない分説得力は持たせる」という言葉はとても良い。
即席で出来るし、ジャジーに演じているように見えるし、覚えておくと役に立つと思う。一応1段目はセルフワーキングで、2段目は軽くテクニックが必要になるけど容易な部類。人前であれば構造的にオフビート中に行うことになるので不格好でも成立する。ただ、不思議に演じるには中々演技が難しいかな。まぁそこはジョセフの話をちゃんと聞いて練習するしかないですね。
ダニ・ダオルティスの『C10』に載っているメモライゼーションなんかとシナジーありそうな気がしますね。
C10 ダニ・ダオルティス(スクリプト・マヌーヴァ)
所感:「C10」by ダニ・ダオルティス(ゆっくり手品がたり)
プレディクション1
観客が混ぜ、言った枚数目から取り出したカードが予言と一致している。
見た目はシンプルな予言。対マジシャン用に考えたトリックということもあってとても不思議。セルフワーキング・・・に近いと言いたいところだけど、状況によってはスライトが必要になる点や、さりげなくうんちゃらみたいな操作があるので練習無しで演じれるようなものではないけど、非常に難易度は低い。
対マジシャン用で考え出されたトリックは、無駄な手続きが多くてだるいトリックになってしまうことも多いけど、これはとても良い塩梅で構成されています。「なんでそんなことするの?」っていうのがない。いいね。
プレディクション2
観客が混ぜて表向きの中から選んだカードが予言されている。
見た目シンプルだけど非常に不思議な予言。得意な人は得意だけど、苦手な人は演じる気にもならないトリックですね。
シンプル・ソート・オブ・カード・アット・ナンバー
観客が見て覚えたカードが、観客が適当に抜き出した枚数と同じ枚数目から出てくる。
セルフワーキングと言ったか?スプレッドしてちらっと見せるタイプのサイコロジカル・フォースを使っているからこその構成だと思うのでさすがにその言い方は無理がある。
最初の部分以外は確かにセルフワーキングと言えるけど、他のフォースやコントロールで代用した場合、何でもそうだけど効果がだいぶ落ちる。人によっては十分かもしれないけど。
後半部の観客が適当に抜き出したカードの枚数を知ることなく、枚数目に移動させれるのはいいなー。
観客への指示が多いので、セリフ運びに注意したいですね。
あと、フォースを失敗したときどうする?みたいな話題になったのに、結局フォースのコツを語り始めるのはやめ給え。アイツは人の話を聞かないって言わなくちゃいけなくなるぞ。
シンプル・マス
3人の観客がストップを掛けたカード3枚の合計数と、4人目の観客がストップを掛けたカードの枚数目が一致している。
数理マジックと言い張って行う完全即席トリック。
カードをパッと当てるわけでないので、現象に好き嫌いはあるかもしれないけど不思議だし有用。後半に、ストップフォースのコツや失敗したときのリカバリー方法の話をしているのでそこも参考に。
ゼイ・マッチ
観客の覚えたカードはこちらに無いと十数枚のパケットを取り除いた後、残ったパケットから1枚のカードを抜き出し、マジシャンはこれだと言うが、観客はさっき除いたパケットにあったという。一見外したかに見えるが取り出したカードは当たっており、除いた十数枚はすべて選んだカードと同じマークのカードに変わっている。
セットが必要だが不思議なトリック。スライトもそこまで必要でない。
イロジカルな操作を行っている部分があるんだけど、錯覚が効いているかと言われれば個人的にはちょっと弱いかなと。見ててわたしがどっちがどっちか混乱したので。マジシャンの後付の説明と、パケットの枚数なんかの情報から推察は出来るので「頭の良い観客には通じる」みたいな部分はあるかと。
とはいえ全体の流れは綺麗で、総合的には良トリックかと。
ダニ・ダオルティスの「カオス・イン・オーダー」(DVD『ファット・ブラザーズ1』収録)をセットありにしてシンプルにした印象。
観客に十数枚抜いてもらっているわけではないけど、これもホフジンザー・プロブレム(ロスト・エースじゃなく観客が引いたカードがすべて同じマークのやつ)って言い張れるかなぁと思ったり。
ホフジンサー・プロブレムって何ですか?(ゆっくり手品がたり)
ソート・オブ・スプレッド・トライアンフ
トライアンフ。
裏表噛み合わせた後、タマリッツのリフル・シャッフルを押し込んで完全に揃えるディスプレイをした後に、バーノンのトライアンフするように変えたもの。
難しいけど非常に説得力は高く、これまでにあったトライアンフ用のサトルティなんかが大体使えるのも強い。
ホフジンザー・エーセス
かっこいい4Aプロダクションからの、ホフジンザー・プロブレム(ロスト・エース)。
ちょびっと準備が必要(観客の目の前でしれっとセット可能レベル)。
プロダクションとロスト・エース部分は構造的に一緒になっているわけではないので、気に入ったらプロダクションだけ取り入れたり、ロスト・エース部分だけ使ったりも可能。
ロスト・エース部で行われていたムーブ、カリー・ターンノーバーのような雰囲気を感じたのでこれは難しい匂いがする。と身構えたけどとても簡単だった。KMムーブとカリー・ターンノーバーを足したみたいな技法。逆向きのカードが残るのがデメリットなのかもしれないけど、上手いことトリックに活かしてますね。
カウント・トゥ・エーセス
4人の観客にパケットを渡し、混ぜたりして1枚取り出すと全員Aである。
観客参加型トリック。セルフワーキングにちょっとスライトを入れると化ける典型かもしれない。
ただちょっと、採用している技法についてもうちょっと狙いを話してほしかったなぁと思ったりも。
シンク・ストップ
3段構成のストップ・トリック。「ストップ」は口に出すのではなく、思ってもらうだけの演出。
メモライズド・デックを使用する手順。とても不思議。
1段目でダニにストップ・フォース(パケットを広げて捨てていくやつ)をスタックを崩さずに行っているんだけど、スタックを使っている人には便利なアイディアだよなーと思いました。
サブコンシャス・ポーカー/10カード・ポーカースタック
観客の覚えたカードを含んだカードをポーカーのように配り当て、ストレートフラッシュになっている。
完全即席で堂々と観客の前でセッティングする。スペインのマジック味を感じる。
サブコンシャスと10カードは原理は同じだけど、最後に示す演出が異なっていて別トリックのように感じる。10カードの方がスライトが一つ増えるので少しだけ難しい。個人的には10カードの示し方の方が好み。
とても便利で良いトリックだと思います。
ポーカーの知らない観客にはどうするって?同じマークで順番に揃ってたら強そう、くらいはさすがにバカでもわかるだろ( ˘•ω•˘ )猿に見せる手品はねぇぞ