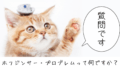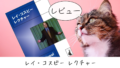トランプマジックをする上で、未だに(2025年時点)おすすめの入門書のひとつとして挙げられる『Expert Card Technique』のPart4-Chapter3、トリックパートの中のエースを使ったトリックのチャプターをすべて読んだのでその感想を。

カードマジックの「おすすめ出来る」入門書って、カード・カレッジが一番新しいくらいで、未だに70年前の本が挙げられているんですね、そんな気はしていましたがびっくりです
Fantia・Creatiaにすでに投稿した記事から、ちょっと都合の悪い部分はカットしてまとめました。
翻訳したものはこちらに公開してあります(サブスク登録者限定です)
Fantia
Creatia
MERLIN’S “LOST”ACE TRICK
MERLIN’S “LOST”ACE TRICKはエース・アセンブリタイプのトリックで、その中でもクラシックな「それぞれのAの上に3枚のXカードを置いて4枚の山を4つ作り、観客の選んだ山にすべてのAが集まる」という現象のカード・トリック。
有名なトリックでありますし、色々なマジシャンが言及したりはするものの、わたし日本語の資料で読んだ覚えないですし、詳しく知らないなって。知ってるけど、それが原典と本当に同じものなの?っていう疑問。
アルマンド・ルセロのDVDくらいでしか見たこと無い気がします。サブスクなどでは野島さんやらシェーン・コバルト氏なんかが言ってたりはしたけど(ここ最近新しいコンテンツをあまり見なくなってるんで情報に疎いのだ)。
英語圏であれば「Expert Card Technique」がありますけど、和訳なかったですよね?
何を持って「MERLIN’S “LOST”ACE TRICK」の派生だと後世のマジシャンたちが判定しているのか知らないですが、おそらくダブル・ディールを使ったAの不在証明とパケットのスタックを同時に行ってしまうところなのかなと。
分割してしまえば技法的には楽になりますが、観客からの見た目を考えると分割せずに同時に行えるのならばそちらの方が良いなとわたしは思ってます。
たまたまMERLIN’S “LOST”ACE TRICKを訳して読んでいたときに、シェーン・コバルト氏のPatreonでルーク・ジャーメイ氏がレクチャーをしていて、エース・アセンブリ(詳しく書くとネタバレになるのでこの表現で)を演じていたのですが、スライト的には異なりますが、プレゼンテーション・構成的にはMERLIN’S “LOST”ACE TRICKを彷彿とする演じ方だったので、やはりちょうどいいなぁって感じました。
翻訳されているものだとPeter Kaneの翻訳本『Combined Card Sessions』、それ以外だとJared Kopf氏がDLC『Merlin’s Lost Ace Trick』を出しているのを教えてもらいました。助かります(*゚ー゚)
コンバインド・カード・セッションズ by ピーター・ケイン 日本語訳版(モジテジ)
Merlin’s Lost Ace Trick by Jared Kopf(Vanishing inc.)
Paper Cuts – Volume 3 by Armando Lucero(Vanishing inc.)
Ace Affinity
現象はクラシックなエース・アセンブリなのですが、コヌー・エースのような観客を引っ掛けるサカー・ムーブのアイディアが含まれていました。
コヌー・エースについて知らない人は以前書いているので、それを読んでもらえばそこそこわかるかなと。
ひとつひとつはそこまでではありませんが、地味にスライトをちょこちょこ常時行っている状態なので、マジックに不慣れな人には難しいトリックかもしれませんね。
何にもしてないけど何かやった感を出すサカー・ムーブのワンハンドカットとか、好きな人は好きですよね。
Ace Assembly
流行りのトリックの最新のやり方(1950年代)と、これまでされていた古いやり方を知ることで、同じトリックを色々な人間が違う考えでアプローチすることで、メソッドがどのよう変わるか見てほしいとかそんなことが書かれていました。
でまぁ、古いメソッドと新しいメソッドの2パターンが解説されているのだけど、新しいメソッドはいわゆる「エース・ボナンザ」と全く同じトリック(3枚配って1枚ずつ3枚置いてーっての)で、今の私達の感覚だとアセンブリじゃなくてプロダクションとかだなぁ~と。これについては特に語ることもない良いトリックなので、あのトリックが収録されていたよ、っていう情報のシェア的なものだと思ってもろて。
それと、古いメソッドとして紹介されていたトリックもボナンザのようなトリックなのだけど、ボナンザのAが配置されていくタネの面白さを持ちつつ、「観客に指示してカードを操作してもらう」という状況下であれば、ボナンザよりもやりやすそうだなと感じました。
デメリットは、演者が覚える操作が多少多い・・・くらいかな。わたしは古いメソッドの方が好みかもしれません。
Anent the Bertram Aces
Anentってなんて意味やろ、と思ったらabout、「~について」の古い言い方らしい。へー(*゚ー゚)
それはさておき、解説されているのはCharles Bertram氏のフォー・エース・トリックで、『The Modern Conjurer』などに解説されていたものだけど、実はそのときクライマックス部分は掲載しなかったようで、今回はクライマックスも載せるぜとかそんなことらしい。
彼ら(ヒューガードさん達)の出した著書ってなんか微妙に、「本人が実際にやっていたのとは違うけど」っていう記述がちょこちょこ入るのが気になってはいるけど、難しいと読み手が出来んだろう的な配慮だと思ってスルーしておく。
現象はいわゆるエース・アセンブリだけど、「配るのは観客」「観客が押さえているマスター・パケットから3枚のカードをスリとってから3枚のエースを送り込むという演出」ってところが特徴でしょうか。
アセンブリで移動したのに4枚のままだと変じゃね?っていう議論があるらしいけど、それは先人が100年以上前(初出は1889年)に通り過ぎた場所だ。
また、クライマックスのアイディアというのは、毎日のように対人で演じているマジシャンが考えたんだろうなっていう感じのもの。演じる機会が多く、観客と近い距離で演じているマジシャンならやってみたらいいよ。
1800年代はそういったトリックが主流だったと聞いてはいますが、観客にわざと疑いを持たせる演出やフェイクも多いですねー。
Streamlining the Sympathetic Aces
「クイーンの夜会」って呼び名の方が通りが良いのでしょうか?まぁ、若い子からこれ系のトリックの名前が出てきたことないので存在を認知してるのかすら怪しいですが、コイン・マトリックスをカードでやると見せかけて、んーなんか違う!ってなるあれです。
ちなみにクイーンの夜会って名称は、はDai VernonのSympathetic Acesである「The Queen’s Soiree」が和訳されたときの名称です。カードマジック事典やアマー先生のイージー・カードの6巻とかに収録されています。わたしはこの文章書きながらアマー先生の実演見て、事典読んできました。
事典に載ってるSympathetic Aces系トリックって割と充実してたんですね。それ読んだら十分じゃないかな・・・。
で、この「Expert Card Technique」に載っている手順はというと、Yank HoeのSympathetic Coinsをほんとそのままカードにしただけ、って感じの手順です。
カードだとスートが4種類あるので、それを観客に分かりやすくするために新聞紙にスートを書くところ(バーノンのSoireeでもやっている。アマーさんはしてなかった)や、上手いこと誤魔化して置くところがカード特有の操作になってます。
トータルで言うとMcCaffrey(古いSympathetic Acesの手順。事典にもあり)とVernonの手順を合わせたって感じでしょうかね。可もなく不可もなく。
この手のトリックで最近のものってまったく思い浮かびませんが、Roman GarciaがDVD『NANOMAGICS』でやっていたやつが印象に残っていますね。
Nanomagics by Roman Garcia Pastur(Vanishing inc.)
The “Slap” Aces
わたしがNate Leipzig氏のこのトリックを知ったのは、松田道弘氏の「あそびの冒険 1巻」ででしたが、そこに書いてある内容とは結構異なっていました。
「Expert Card Technique」記載の手順はある程度変更していると述べられていましたけど、松田氏も参考文献に「Expert Card Technique」を挙げていたので、間違っていたのか、別の本に書いてあった手順を載せて「Expert Card Technique」のは軽く目を通していただけだったのかとか、その辺は分かりませんが、ともかく異なっていたのでこのバージョンが気になる人はチェックでもどうでしょうか?
ちなみに現象は、4枚のAをデックに戻した後叩くとデックからAがすべて消え、観客に無いことを検めた後、デックを叩くと1枚ずつ出現してくる。というもの。
「Expert Card Technique」と「あそびの冒険」で異なっている部分は
- 観客2人にAを2枚ずつ持っていてもらうんですけど、「Expert Card Technique」はマークに指定なし、「あそびの冒険」は指定あり。
- 4枚とも消えたときの検めの手法が根本的に異なる。
- 4枚目のAの出現が「Expert Card Technique」では2パターンあり(「あそびの冒険」に記載されているのはExpert Card Techniqueに記載されてる手法の片方のみ)。
そんなところ。あと「Expert Card Technique」には手伝ってもらう観客に向けるべき態度とか、客選びに失敗したときの対処とかそういうことにも言及されてました。
Le Temps Four Aces
普通のエース・アセンブリなのだけど、Denis Behr氏の「Conjuring Archive」にあるデータでは一番古いLe Temps Switchの資料。内容の殆どはスイッチの解説です。
かなり詳細に解説されてい・・・されてるか?細かな指の動きとかではなく、前後の動きやジェスチャー、どんな文脈で行う動きなのかという部分に焦点が当てられた解説になっていて、アスカニオをはじめとするスペインの人達がよくやる動きを思い出しました。
Passe-Passe Aces
カットして4枚のAを出すと宣言するが、ハート、ダイヤは成功するものの3、4枚目は失敗する。失敗した2枚のカードがハートとダイヤのAに変わり、ハートとダイヤのAだったはずのカードがスペードとクラブのAに変わっている。
デックを使った手順で、Aを使ったトリックのオープナーに使ったり、その後デイリー博士のラスト・トリックを演じたりとかいいかもしれませんね。
んーそんくらいかなぁ。
The Migratory Aces
デックをカットするたびに、その場所からAが出てくる。その後、4枚のAをデックに戻すと、演者のポケットからAが1枚ずつ出現、デックからAは消えています。
エースの出現と、ダイ・バーノンのトラベラーズの組み合わせ。
バーノンのトラベラーズの初出が1950年の「Stars of Magic vol.6-3」、この「Expert Card Technique」は1950年に大量に加筆されて第3版刊行(1版が1940年)。
この「Expert Card Technique」って、作者が明記されていない作品のほとんどがチャーリー・ミラーかダイ・バーノンって言われていたり、実はゴーストライターがチャーリー・ミラーだとか、未公開で出すつもりがなかったバーノンのトリックが勝手に載せられたとか色々曰く付きでもって、絶妙に簡単になるようにアレンジされてるのもなんかとても面倒。
まぁ、その辺は置いておこう。長くなる。
それもよりも許せないのは、まじで意味のわからない動作があったこと。
なんやねんその表現は。頼む、挿絵入れてくれ。何度そう思ったか。2週間位作業止まった(盛った。そんなには止まってない気もする)。辛い。ちなみに最初のAを取り出すとこ。
トリックの内容に全然触れてねぇ。
うーん、現象そのまんまだよ。
ヴァーノン・リベレーションズの中でバーノンが、トラベラーズを演じたとき全然受けなかったけど、あることをしたらとても受けるようになった。手品をしない観客からすると、気になるのはそういうところなんだ、っていう話をなんとなく思い出しました。
Solo Flight Aces
一言でいうとコリンズ・エース。
前半はコリンズの原案通りだけど、後半にダイ・バーノン考案の手法が採用されています。
これは、4枚のXカードが1枚ずつAに変化していくっていう、Cy Endfieldの「Aces for Connoisseurs」でも採用されている方法ですね。
コリンズ・エースを演じるとき、クライマックスをどうするかいつも悩みますけど、このバーノン案はいつも候補に入れてしまうので、それほど完成されているんだなと。
ちなみにわたしは、コリンズのMチョイスを使う方法、Francis Carlyleの観客の指定した場所に集める方法、このバーノンの方法のどれかを演じることが多いですね。
Cy Endfield’s Entertaining Card Magic Lewis Ganson
The Nomad Aces
現象はシンプルなクラシック・エース・アセンブリ。
茶番を使ったサトルティや、この時代ではまだその名称が出来ていないが、イントランジット・アクションの動きも使われています。
The Charles Miller Aces
上記トリックのヴァリエーション。上記のタネを知ってる人だろうが絶対に引っ掛けるとかそういう気概の作品。
フェイスド・デックの原理を使った最も古いトリックだとかなんとか。加えて、サリバ・メソッドを使ってる作品だというところも、貴重な資料なのではないかなと。
Cops and Robbers—a Variation
4枚のキングを探偵に例えてテーブルに置いておき、観客に1枚選んでもらう。テーブル上の4枚の上にデックに乗せて広げると、4枚のキングだけが表向きになって1枚のカードを挟んでおり、それが観客のカード。
タイトルは警官なのに解説はずっと探偵と言ってるのが気になったけど、昔は一緒の職業だったとかそんなんかいね?
現象の見た目はとてもシンプル、現代だとところどころこのやり方の方がいいよね、って部分があるけど、良作だと思います。
同書の別ページで解説されているリバース技法を使うのですが、ミゲル・ゴメス氏の『The Joy of Magic』で使われてる技法のタイミングが異なる感じの技法です。