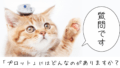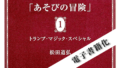- カードマジック事典ってどんな本?
- 新版があるみたいだけど違いは?
- 結局の所どうですか?
- カードマジック事典:おすすめの収録トリック
- 嘘発見器 Lie Detector
- コレクターズ Collectors by Derek Dingle
- トライアンフ Triumph by Dai Vernon
- ライジング・カード② Rising Card by Ken Krenzel
- 差し込んで当てるカード① Card Stab by Max Malini
- どこにもあってどこにもないカード① Everywhere and Nowhere by J.N.Hofzinser
- 予感 Premonition by Eddie Joseph
- カードの読心術① Out of Sight-Out of Mind by Dai Vernon
- 差し込んだカードと一致するカード Stabbed Coincidence by Larry Jennings
- Aの出現① Ace Bonanza
- 同時に現れるカード③ The Power of Thought Paul Curry
- 赤と黒 Out of this World by Paul Curry
- アンビシャス・カード② Solid Deception by Paul Harris
- 水と油① Oil and Water by Edward Marlo
- 水と油④ Oil and Queen by Roy Walton
- 4枚のA② Four Aces by Stanley Collins
- 4枚のA③ Saturday Aces by Nick Trost
- 4枚のA④ Aerodynamic Aces by Bruce Cervon
- ポケットへ通うカード② Homing Card by Francis Carlyle
- ポケットへ通うカード③ Travellers by Dai Vernon
- ポーカー・デモンストレーション① Poker Demonstration by Dai Vernon
- ジムナスティック・エーセス The Gymnastic Aces by Paul LePaul
- ひっくり返すA① Twisting the Aces by Dai Vernon
- ひっくり返すA② Maxi-Twist
カードマジック事典ってどんな本?
1983年に初版が発行されたマジックの解説本。
2016年には新装版も発行され、長らくマジック愛好者たちの間で「定番」「必読」「バイブル」と言われ続けている本。
技法編とマジック編に分かれていて、技法編は全体の約1/3程度のボリュームで、マジック編は残りの2/3ほど。
「付録」としてギミック・カードについても触れられているがこれは10p程度である。
カードマジックをする上で必要になる基礎的な技法は大体網羅されており、収録されているマジックは古い作品ばかりだが良作が数多く収録されている。

ちなみに「辞典」でも「字典」でもなく「事典」である
新版があるみたいだけど違いは?
旧版は箱付きのハードカバーで、新版はソフトカバー。
サイズは箱・ハードカバーのせいで旧版が大きめに感じるが大差はない。
気になる内容なのが、実は内容はまったく同じで差なんてない。
旧版にあった「記載の間違っているトリック」もそのまんまである。
ハードかソフトか、自分が読みやすいと思う方を選ぶと良い。

自分が覚えている限りでは間違って記載されていたトリックはひとつだが、他にもあるらしい
結局の所どうですか?
素晴らしい本であることには違いないが、手放しで勧めるのはのはよくない本であると思っている。
簡潔にいうと「能動的にマジックを習得することに慣れている」「研究者気質の人」「前二者のような人達と仲良くなりたい人」といった層向けで、他の資料と合わせて使用する本だと思っている。
以下はもうちょっと細かく感じたことを羅列。
・安価(中古品含む)かつ容易に入手出来る
・必要になる技法は一通り載っている
・収録されているトリックが多い
・現在人気のあるトリックの「原案」を知ることが出来る
・今演じても色褪せない「古典」トリックを覚えれる
・読んでいるマジシャンが多いので、共通の話ネタになる
・文章が読みづらい
・解説はそこまで丁寧ではない
・記載されている技法・トリックを「改良したもの」が現在では存在していることがある
・間違ったまま記載され、訂正されていない箇所がある
・トリックの考案者から許可を取らずに作った本である
このあたりは留意するべきだと点かと思う。
ある程度学んだ人であれば、分からづらい文章でも動きがそれなりに理解出来るし、知らない技法があったときに調べたり、現在人気のあるトリックの元ネタを学んだりも出来るので、自発的に深く研究したいという人にはおすすめできると思う。
一方で、手軽に最新の面白いトリックを知りたいという人や、動画をメインの教材とした「受動的な方法」で手品を覚えてきた人だと、目を通すのですら面倒だと感じると思う。
「おすすめのトリックあります?」と調べる前に口に出る人は、大人しくDVDやyoutubeで探した方が無駄がない。
もし完全初心者がこの本の購入を検討しているや、子供がマジックに興味を持ったので買ったあげようか考えてる、という人はこれらのことを踏まえて少し考えて欲しい。
頭を使って考えたいって人なら○。
楽して色々覚えたいっていう人は×。

スタイルに合わせて購入すべし
これ以降は、実際収録されている作品の中からおすすめというか、これに目を通しておくといいよ!って思った物を紹介。

長くなるので、持ってない人・買わないと思った人は、ここから先見なくてもいいと思うよ
素通りしづらいように少し空間あけておいた。
カードマジック事典:おすすめの収録トリック
それでは載っているトリックの中からおすすめをいくつか。
演じやすいとか、簡単にウケるとかだけではなく、おすすめ出来る面があるトリックや後に重要になる原典的なものとかを。
「知ってても損はない作品」とか「隠れた名作」とかそういうのを多めに。

収録されてるページはちょっと割愛。目次で調べてくださいな
嘘発見器 Lie Detector
演者は後ろを向いた状態で、観客の「声」を頼りに覚えたカードを当てるという演出のトリック。
文章で読んだだけではおそらくほぼ確実に見過ごすと思う。
メンタルマジックが好きな人にぴったり。
観てる側からすると、手がかりがマジで声しかない。「ウワッ気持ち悪!!」って感じる(良い意味で)。

これは出来ることなら、読む前に誰かに実演してもらうといいのぜ
コレクターズ Collectors by Derek Dingle
4枚のAを使って3枚のカードをサンドイッチして当てるコレクターズ現象。
数多く考案されるコレクターズの中における先行作品のひとつ、歴史を知る上で知っておいて損はないと思う。
トライアンフ Triumph by Dai Vernon
裏と表をバラバラに混ぜてから当てる「トライアンフ」の名前の由来であり原点。
古くからあるトリックだが、今演じても他の人気手順に一切引けを取らない完成度である。

覚えて演じるにも良いし、歴史を知る上でも知っておいて欲しい

ライジング・カード② Rising Card by Ken Krenzel
カードがひとりで動いてせり上がってくるやつ。

覚えておきな、絶対使うで!ってレベルで重宝する
差し込んで当てるカード① Card Stab by Max Malini
「マダム、その傷はマリニが付けたものだと言えばいいのです」
という名言はこの手品が生んだものだ。

え?知らない・・・?マジかぁ・・・。だったらどこかに書いておくよ
ナイフを使って複数枚のカードを次々と当てていくトリック。
テーブルに傷が付くので演じない方が良いと思う。あくまで歴史的なおすすめ。
どこにもあってどこにもないカード① Everywhere and Nowhere by J.N.Hofzinser
違うカードが選んだカードに変わったり、元に戻ったり、別の場所に現れたりと、翻弄するトリック。
後世に色んな改案を生んだ作品。
演じるには準備的も難易度的にもハードルが高いので、研究メインでのおすすめ。

これが後世のマジシャン達によってどういう変化を遂げていくか、時の流れに思いを馳せると良いよ
予感 Premonition by Eddie Joseph
観客の選んだカードだけが無い。というトリック。
数々の改案を生むことになる作品の原案。
演じるには準備が面倒すぎるけど、知っておいて損はない。

原案の時点で観客からの見た目は完成されてる。ただ「面倒」なのが欠点なのである
カードの読心術① Out of Sight-Out of Mind by Dai Vernon
観客が観て覚えたカードを当てるトリック。
数々の改案が生まれたが、原案のまま演じても強力。
気になって原文を読んだのだけど、ほぼほぼ正確にそのまま訳されていました。原文から読みづらいのである。

しかも即席で演じれるので戦力としても抜群に強い
差し込んだカードと一致するカード Stabbed Coincidence by Larry Jennings
観客の選んだカードをデックに差し込むと、差し込んだカード・その上下にあるカードが同じ数字のカードで、予言のカードもその数字だったのだ!と4枚揃うトリック。
有名なあのムーブを使ったトリック。覚えておいて損はないと思うよ。
Aの出現① Ace Bonanza
セルフワーキング・トリック。
この後にエース・アセンブリ系のトリックを演じると話の辻褄が綺麗にあうよ。

ルーティンってものを考え始めた人達へおすすめするよ
同時に現れるカード③ The Power of Thought Paul Curry
2デック使うのでスルーしそうだけど、メンタル系トリックの名作。
2デックを同時にめくっていくが、観客の選んだカードだけ両方のデックから同時に現れる。

ちょっと演じてみ?改案も色々出てるけど、まずはこれを
赤と黒 Out of this World by Paul Curry
みんな大好きな傑作トリックの原案。
原案は演じるのにちょっと面倒なところがあるけど、一度手順を並べてみると良いと思うんだ。
アンビシャス・カード② Solid Deception by Paul Harris
これも名作だ。オムニデックって知ってるかな?あれは普通のトランプでやるとこうなるよ。
上手くやれば、すでに演じてるアンビシャスカードの最後をこれにするっていう手もありだ。

これはこれで違う味があるのですよ。現象は読んだ人だけのお楽しみで
水と油① Oil and Water by Edward Marlo
赤と黒が分離するオイル&ウォーターの最初の姿。
難しいけど、上手く演じると不思議や。
上手く出来なかったら他の手順を覚えてから、また再挑戦すると色々発見があって良い。
水と油④ Oil and Queen by Roy Walton
オイル&ウォーターにクライマックスを足した有名な改案。

これも覚えておきな。演じてもよし
4枚のA② Four Aces by Stanley Collins
エース・アセンブリの一種。一度消えてから集合して現れる。

コリンズ・エースと呼ばれる現象の原案・・・と言いたいが、実は改案を日本で翻訳したときに名前を間違えて掲載されたという話がある。
とはいえ、このトリックの存在は知っておきたい。
4枚のA③ Saturday Aces by Nick Trost
マニアが好むスローモーション・エーセスというプロットのひとつ。
少し難しいが、知るためにもちょっと手順を並べてみてはどうでしょうか。
4枚のA④ Aerodynamic Aces by Bruce Cervon
インビジブル・パーム・エーセスやオープン・トラベラーズと呼ばれる現象のひとつ。
難易度は高いかもしれないけど、上手に演じれると素晴らしい。ちょっと挑戦してみてほしい。
直接関係はないが、このトリックに関わる独り言記事があるので貼っておきます、気になったらどうぞ。

ポケットへ通うカード② Homing Card by Francis Carlyle
ポケットに観客のカードが移動するトリックの代表。
シンプルながら強力な手順。おさえておきたい。

ポケットへ通うカード③ Travellers by Dai Vernon
ポケットに移動するカードの代表例その2。
ミスディレクションの習作。なんて言われ方もしている、4枚のAが色々なポケットに移動するトリック。難易度は高いけど、ミスディレクションというものを理解するのには非常に優れている。
後世の作品に「トラベラーズ」という言葉がよく付いているのはこの作品が元ネタ。
ただ、ここで用いられるヒューガード・トップパームのやり方が分からず詰む可能性がある。
別で調べるか、詳しい人に代替手段を習うなりが必要。

正直、突然マニアックな技法持ち出してくるのはひどいと思っている
「4枚のA④ Aerodynamic Aces」ところに貼ったリンクの記事、このトリックにも関わっているので貼っておきます。すでに読んだ人はスルーしてね。

ポーカー・デモンストレーション① Poker Demonstration by Dai Vernon
ポーカーのイカサマを擬似的に再現するみたいなトリック。
名作なのであるが、これを覚える際は注意して欲しい点がある。
原案は、セットが非常に覚えやすい点が特徴のひとつなのだが、実際読んでもらうとそんな要素微塵も感じれないと思う。これは日本語に翻訳された際に、セットに関した部分がカットされたせいだと思われる(書籍『The Dai Vernon Book of Magic』なんかには詳しく載っている)。
そのまま覚えようとする前に、そういった注意点があることを知ってほしいと思いました。
ジムナスティック・エーセス The Gymnastic Aces by Paul LePaul
4枚のAがデックからビュンビュン飛び出してくる。
ビジュアルなエースプロダクション。おすすめ。
「振るとエースが出るやつみたい!」ってよくリクエストされます。

力加減を誤るでないぞ
ひっくり返すA① Twisting the Aces by Dai Vernon
4枚のAだけを持ち、1枚ずつひっくり返るトリック。
みんな大好きなあの「パケット・トリックでよく使われる技法NO.1」はこのトリックがあったから有名になったといっても過言ではない。

歴史的にも重要な作品だけど、今演じても普通にすごく不思議です
ひっくり返すA② Maxi-Twist
「Twisting the Aces」にカードが別の数字に変化するというクライマックスを加えた作品。
最後までありがとうございました。
1作品1時間ペースでやったら1日で終わるように24作品選んでみました。
よかったら参考にしてみてください。