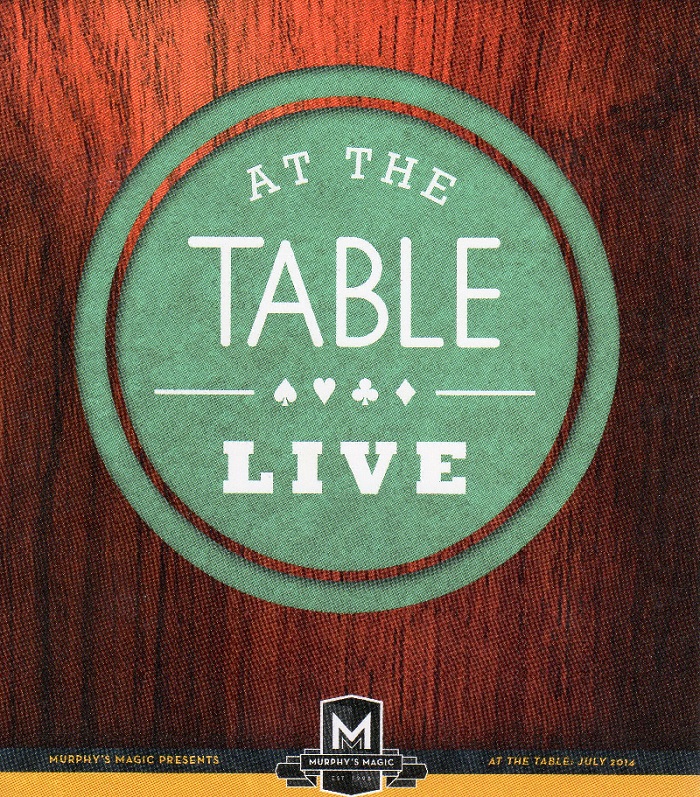At the Table Live Lecture Vol.2 – (JULY2014) – Hannibalとは?
2014年7月に行われたmurphy’s magic主催のオンライン・ライブレクチャー、Hannibal(ハンニバル)回。
正直あまり知らないので、公式サイトへのリンクを貼っておく。
収録時間は約3時間半である。長い。
所感
Lethal Weapon
観客の思い浮かべた有名人を当てるメンタルマジック。
ギャグでのらりくらりと笑いを取った後に、最後にはきっちり当てる。
面白いのだが、日本語でそのまま行うことは不可能。やるならばガッツリと変更しないといけない。
二川滋夫氏、ヒロサカイ氏、斎藤修三郎氏あたりが日本語版を作っていないのであれば、多分日本語版は存在しない。
実演でやっているような完全にフリーで思い浮かべてもらったように見える下りは、ちょっと事前準備的なあれが必要なので・・・うん。
Cards Across
2人の観客に10枚ずつカードを持ってもらい、観客の引いたカードの数字の分だけ移動させる古典的なアクロス。
見た目の大筋はデビッド・デバンの手順と大体同じ。
デバンの手順はパームが1回で済むけど、こっちはまぁ結構やる。
上手いことタイミングをずらしてるような気もするけど、なんとも言えない。
パームは手の大きさに頼った力技感がある。参考にはならん。
ステージに上がる2人の観客は女性が選ばれ、カードはブラジャー?の中に入れてもらう感じの演出になっている。
解説では不快・強制してると思わせないための工夫、そして「こういうシチュエーションでは絶対に演じない」なんてことについても話している。
話してる通りの適切な状況で演じれば確かに良いのだろうが、まーうん、わたしにはそういうの合わんな―。
シモネタをきちんと考えて行っている人をあまり知らないので評価しづらいのだが、参考にしたいと思う人はどうぞ。
以降の話に出てくるとんでもない観客は、この手順のためにステージにあげた女性客だ。
Audience Questions
質問とか色々。
ハンニバル・レクターよりも前か?などの質問が飛び出しちょっと面白かった。
プロマジシャンとして活動する上で、氏が行ってきたマーケティング・ブランディングについての話とかが参考になるのではないだろうか?
また、ステージにあげた観客に会場の笑いをすべて持ってかれる話なんかは面白かった。
この辺りでちょこちょことクラシック・フォースやトップ・チェンジなどの解説もされる。
そこまで詳しいものでもないが、色んな人のやり方を研究したい!みたいな異端者のためにもそういう情報だけ残してく。
The Trick That Can Not Be Explained
観客の言ったカードが、観客が選んだ場所から、観客の名前の分だけ配ると現れる。
そのまんまですが、メモライズド・デックを「説明できないトリック」に使った手順。
解説はそこまで詳しくない。氏はアーロンソン・スタックを使っている。
ネモニカの本を読むと色んなすごいのが載ってるぜ!だってよ。
Pringles Act
プリングルス(ポテトチップス)の短めの缶を使ったアクト。
カード・アンダー・ザ・ボックス(プリングルス)とワンカップ・ルーティンの2つから構成される。
カード・アンダー・ザ・プリングルス
3回缶の下に移動後、マジシャンのポケットへ移動したり、眼鏡に挟まっていたり、デックが缶の下にあったりとバリエーション豊か。クライマックスではサインしてもらった状態で四つ折りになりプリングル缶の中へ移動する。
下のアングルからパームを見せてくれるなどしているが、そもそも手の大きさがぜんぜん違うので参考になんぞならん。
全体的に結構ざっくりした解説なのだが、マイケル・クロースのDVD『シグネチャー・エフェクト』、あれでは技法だけきっちり解説されて手順自体の解説が全くなかったのだが(「おでこと塩瓶」のこと)、あれと組み合わせると割と補完しあえるのではないかと思った。

新規性のようなものはないが、この手の手順で出来る現象は大体網羅されているの参考にしやすい。

ワンカップ・ルーティン
小振りなじゃがいもとプリングルス缶を使ったワンカップ・ルーティン。
ファイナルロードされるアイテムはプリングルスでおなじみのフレーバーの素材がそのままドーン。
と思っていたけど、じゃがいもじゃねぇよく見たらトマトだ。なんでじゃがいもと間違えたのか。
POTATOとTOMATOを聞き間違えるだけならまだしも、見間違えてもいますからね。
ダイ・バーノンが「カップから出したとき、なぜか一番受けるのはじゃがいも」と言っていたが多分それが引きずっているんだろう・・・。
氏がファイナルロード用のアイテムをひとつ忘れたときに行ったという、即席で行えるファイナルロードのアイディアが非常に便利。
トミー・ワンダーの「ツーカップ・ルーティン」にも通じるアイディア、良いと思います。
Sleight Club Convention
理論というか意見交換とかについての話。
厳しい意見を遠慮なくぶつけ合える交流じゃないと成長出来ねぇ。みたいな内容。
表では絶賛してるけど、裏で文句言うのはいけませんよね。
わたしは遠慮なく、悪いところは悪いと言うように心掛けたい(常識的な範囲で)。

それ既存のとどこが違うのかちゃんと説明してー!
根本的にそれ面白くないよー!?
ベリグッド| |Д`)b
Example On Emotions
物語に乗せたシリンダー・アンド・コインの手順。
マーブルチョコのような見た目のキャンディをコルク代わりにし、容れ物の筒をシリンダーにして行う。ちなみにコインは3枚。(あまり有効活用されていなかったが、針金にキャップを付けた子供の手作り魔法の杖もあった)
不思議ですが解説はなしです。
通常だとコインは4枚ですが、氏の手順は3枚になっている。
やっぱり3枚だとやりやすいだろうか?でもマジシャンからしたらちょっとロマンが足りない気もする。
シリンダー・アンド・コインいいなぁ・・・。実は用具持ってないんですよね―。
The Shoe Maker
シリンダー・アンド・コインで語っていた物語の続き。
紙幣を折っていくと靴になっている。
これは手品ではない( ˘•ω•˘ )
演じる際に語られる物語はなんと言ったらいいのか「子供の頃に見た魔法」ってところであろうか。
ストーリーに乗せてマジックを演じるスタイルのマジシャンには参考なるのかもしれない。
また、自分らしいアクトを作るには?ということについての氏の考え方も語られる。
最後に
3時間半、大体英語で喋っているだけなので英語弱者にはまじで辛いと思う。
映像だけで理解できるのはプリングルス・アクトとカードアクロスだけではなかろうか。
個人的にいいなーと感じたのはワンカップ・ルーティンでのファイナルロードのアイディアと、カード・アンダー・ザ・某の構成の仕方の参考例がひとつ増えたあたりかなと。
マジシャンのキャラクターや世界観といった他のマジシャンとの差別化についての話なんかについて熱く語ってくれているのだが、現在だとそういった内容の理論書は日本語でも結構読めるようになっているので、わざわざこのライブレクチャーを選ぶ必要はないかなと。
またプロとして活動する上でのマーケティングやブランディングについても話している。どうも日本だと(2020年現在)この辺りを考慮しているプロがちょっと少ないらしい(そんなのプロじゃないと思いますけど)ので、もしかしたら参考になる人が居るかも?
Harapan Ong氏がレビューで10点満点中4点という低評価を付けていたので、その辺も考慮に入れてどんぞ。