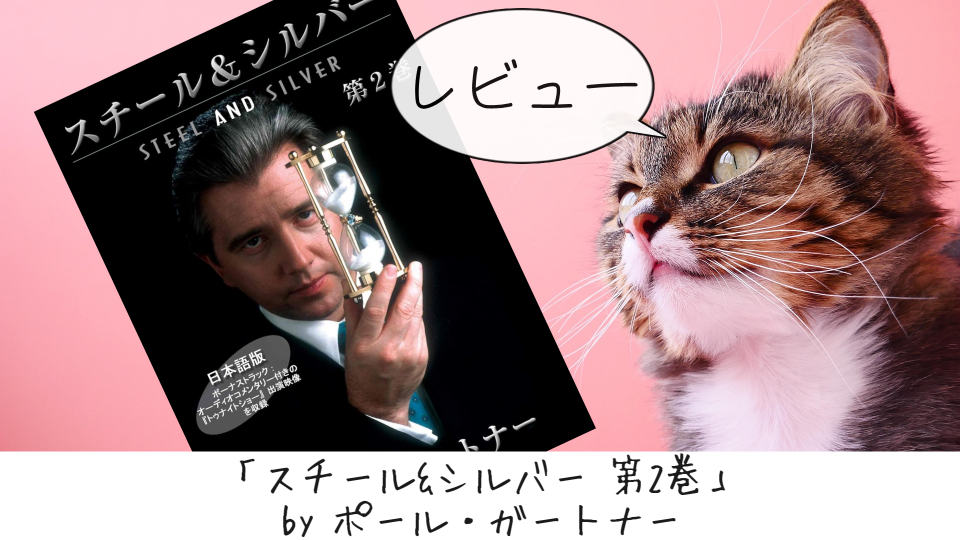Steel & Silver Gertner – Volume 2 by Paul Gertner
Paul Gertnerの同名書籍『Steel And Silver』の映像化。3巻+ショーのみ収録の1巻の、実質4本出ている内の第2巻で、氏のFISM act(1985年マイクロ・マジック部門1位)を解説している巻。
FISM actが解説されているということで、この巻だけを購入した人も多いらしい。
関連記事
【レビュー】スチール&シルバー 第1巻 by ポール・ガートナー
【レビュー】スチール&シルバー 第3巻 by ポール・ガートナー
総評的な
全体的な傾向はやはりクラシックなマジックをガートナー氏が演出したものという感じ。べらぼうに難しいということはないけど、元の手順などからは多少難しくなっています。
クラシック・パスやサイド・スチールやらフェイク・パスというような技法もちょこちょこ出てきますが、その辺の基礎的な技法については解説されないので知ってるの前提だと思っておいたほうがいいです。
FISM actについては完全に解説されていますが、大事な舞台で演じる用のだけあって用具を揃えるのが大変だったり、準備が大変だったり、砂時計が可哀想だったりしてハードルは高いですが良いものです。
FISMアクト
FISMアクトを構成する手順の解説。
リング・オン・アワーグラス
観客の指輪が砂時計のくびれに入ります。
観客の記憶には確実に残るだろうけど、とても準備が面倒なトリック。
演技の度に砂時計を叩き割る必要があるのでコスパも悪い。
カジュアル勢には無用の長物だけど、大事な場で観客にインパクトを与えたければどぞ、っていう感じ。
ちなみにロードのときを始め、諸々の動作を行うときの体勢などきちんと考えられています。さすがです。
ザッツ・レディキュラス
テーブルのカードの下にコインが移動し、クライマックスにはコインがめっちゃ出てきます。
最初のコインがカードの下へ移動する部分は少し野暮ったい感じがし、見慣れたマトリックスの配置なのにマトリックスしないのがモヤモヤする人もいるでしょうが、クライマックスの畳み掛けはとても良いです。
ちなみにクロースアップ・マットではなくて、下が硬いパッドを使って且つ、ちょっと細工も必要。普段から硬いパッドを使っている人だとそこまで関係ないだろうけど、普段がマット使いで「これやりたい」、って思った人はそこ注意。
リード・マクリントック氏が、この「ザッツ・レディキュラス」やディーン・ディルの手順に触発されたトリックを『コイン・オベーション』で演じているので、類似の手順を知りたい人はそちらもどぞ。リード・マクリントック氏のは、面倒な下準備が不要な分、スライト的にべらぼうにしんどいですが。
コイン・オベーション 日本語字幕版 リード・マクリントック(Amazon)
X-Plosion by Dean Dill(Vanishing inc.)
Elegant Close-up Pad by TCC Presents(Vanishing inc.)

Dean Dillのコインが出てくるやつって言ったらあっちの方だろ!って人が居ると思いますが、あっちの動画、ギミックの精度をドヤ顔で説明するやつだったので紹介しづらかったのだ。
あと硬いパッドって意外と知らない人いるかな?ってことで、例としてTCCのやつを貼っておいた
カップ&ボール
氏を代名詞ともいえる、鉄球を使ったカップ&ボール。
言わずもがなの名作。
カップとぶつかると音がする鉄球を使っているので、ぱっと見は普通の手順のように感じるけども、操作が割と異なっています。
実演映像がそこらにあるのでそれを見てもらって。

Fool usの映像ではクライマックスが増えていますが、FISMアクトはでかい鉄球が出てくるところまでです
鉄球いっぱい使うし揃えると高いだろうなぁ・・・って思ってたんだけど、鉄球て意外と安くね・・・?マジックショップでファイナル・ロード用のボールとか買うよりも大分安上がりじゃ・・・?
More Routines
Fismアクト以外の作品。
リバース・マトリクス
四隅にコインを置き、それぞれの上にカードを乗せて行うバックファイア・マトリックス。
コインの移動はフェイク・トス。使用するエキストラなどの枚数が大分多く、今だと色々な手順が出ているので、もっと手軽でビジュアルで簡単なものもありそう。わざわざこの手順を選ぶ意味はなさそうに思えます。
ブラックジャック・サプライズ
ブラックジャックの話をしながら、ポーカーにします。
ブラックジャック演出の「ギャンブラーvsマジシャン」。演出が気に入れば。
ちょこちょこ難しめの技法が入ります。
バウンス・アセンブリー
2枚のカードで行うコイン・マトリックス。
オーソドックスなコイン・マトリックスを、テンポはそのままに2枚のカードのみで行い、4枚集まった後に1枚ずつ逆戻りさせていくことが可能。
なんかこう、これが発表されるまでの間にチンカ・チンクで同じことやった人絶対居るだろ!ってなる。ありそう。ガートナーさんが最初だったらごめんなさい。
Sコインを使うけど、無くても出来なくはないし、見た目はとても良いので気に入ればどぞ。わたしはちょっとやりたい。
スペルバウンド
左手の指先に持った銀貨が銅貨に変化します。
スペルバウンドの技法。変化2回がワンセットになっていて、バーノンのスペルバウンドのように交互に手のひらを検めることが出来ます。
カード・イン・キャンディボックス
アンビシャス・カード後、キャンディボックスから四つ折りになって出てきます。
有名どころのトリック。
ゴディバの箱に少し細工して使っています。ゴディバにキャンディってあったのか?まぁあったのかな。公式には見当たらなかったけど。
原理的にはトミー・ワンダー氏がやっていたのと同じなんだけど、比べてしまうとさすがに見劣りする。確かに箱や折られたカードは小さい方が見栄えが良い(トミー・ワンダー氏が言ってた)。
トリック自体は良いものなので、他のを知らなければどぞ。トミー・ワンダー氏のとかを知っていたら、わざわざ見る必要はないかな。

このゴディバが一番近いのかなぁ
特典映像
1巻と同じ番組への、1年後の出演映像。1巻と同じく通常音声と、オーディオ・コメンタリーの2種収録。
出演のギリギリまで押してて出番がないかもしれないと言われていて、直前に演技時間5分と言われて内容を決めてスタートしたとのこと。
時間に合わせるため焦っていたらしく、出来は良くなかったとオーディオ・コメンタリーで自分の演技に駄目だししていますが、逆にそれがとても参考になります。
コインアクロスで観客の手の上で現象を起こすのがベスト、と思っている人なんかは、こういった状況ではマイナスになるっていうのとか、役立つ情報なのではないでしょうか。なるほどなー。

そしてベテランMCは手品を知らなくとも、視聴者によく見せるすべを心得てますね