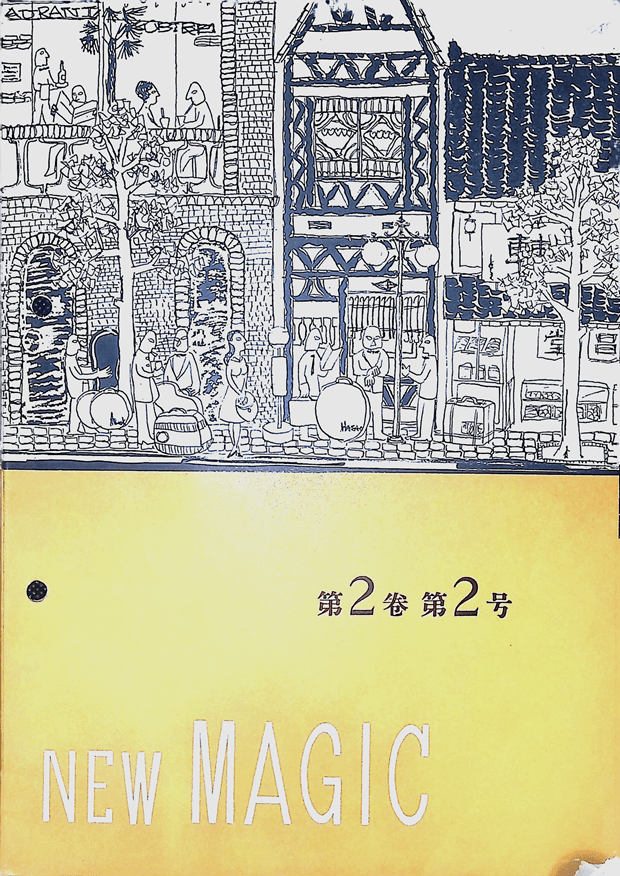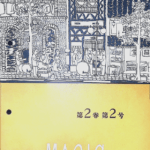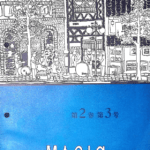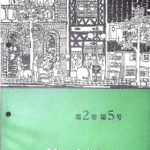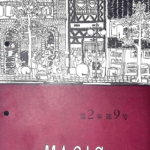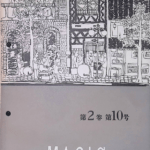石田天海氏、フロタ・マサトシ氏らが中心となって作られていたマジック誌。
後に残しても恥ずかしくないような奇術誌を、日本人の手で作ってみたい。というコンセプトのようで、明治・大正時代に流行した同人誌のシステムを参考にして「10冊ごとに合本にする」という形にしたそうな。
極力手元にあるものは内容を残そうとかそんな感じです。
Fantia投げ銭プラン加入者用の特別ページはこちらに→パスワードはFantiaにあります。
第2巻第2号
奇術の中のパントマイム
フロタ・マサトシ氏のコラム第4回。演技中の「立ち方」についてです。
ラウンドテーブルによる エレベーター・カード 其のⅠ(厚川昌男)
編集部の前置きでは「ルーティン」と紹介されていたけど、技法の解説のみ。
ここでは名称が出てきていないけど、後の作品集では「フォールス・ドロー」と呼んでいた技法。
ちなみにですが、厚川氏は「泡坂妻夫」というペンネームで活動されていた日本の推理作家です。名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?奇術愛好家としてもよく知られていました。

ゆき
興味がありましたら、書店なんかで名前を探してみてはどうでしょう。
ちなみにわたしは、「フォールス・ドロー」を『泡坂妻夫マジックの世界』という本で初めて知りました。
エレベーター・カード 其のⅡ(フロタ・マサトシ)
スペードのAから4までカード4枚とデックを使ったエレベーター・カード。
エレベーター・カードとかペネトレーションという名前で有名なトリックを、4枚のカードで行うもの。
デビルズ・エレベーター(ブルース・サーボンの)なんかは4枚で行うエレベーター・カードだけど、あっちはパケットでしたね。
こちらはデックを使い、本当に3枚のエレベーター・カードをそのまんま4枚に増やした感じです。導入部には「其のⅠ」で解説されていたフォールス・ドローを使っているので、修得したらこちらを練習とかにすれば。
エレベーター・カード 其のⅢ(ふくしま ひろき)
現象としては「其のⅡ」と同じ、4枚とデックを使うエレベーター・カード。
導入や途中の処理で別の技法を使っています。
指にかえるリング(石田天海)
指輪が消えて観客の指に戻っている。
いわゆるエリスのリングを使った手順。ビリー・ムラタ氏と一緒に考えた手順なんだとか。
エリスのリングを買った時に付いてくる手順と同じですが、もしかしたらこれが原典だったりするのでしょうか。
エリスのリングは発売時、ウォンドとリングの手順に使うためだったようで、もし観客の指戻る使い方の初出がこの手順だったとしたら面白いですね。
第2巻第3号
奇術の中のパントマイム
フロタ・マサトシ氏のコラム第5回。立つ時の姿勢や日本人の体型についてなど。
コインのルーティン
来日したマジシャン(ビリー・ムラタ氏)とメンバーが夕食会をしたときに、メンバーが披露したコインマジックをルーティンにするとしたらどう構成したら良いか?と言った話になり出来上がったネタとのこと。連続で演じることが出来るようになっています。
元がバラバラのトリックであるため、巧みな構成になっているかと言われれば粗いと言わざるを得ませんが。
①コインの裏と表
コインマジックを始める時の導入に関する演出のアイディア。
話のネタのストックにでも知っておいたら使うかなーみたいな。
②消えるコイン
1枚のコインが消えますが、前述の話題を演出に使っています。
③コインは再び消える
コインが消えるだけですが、この手法は強いんですよね。
最近(2023年辺り)だとAvi Yap氏が使っていたのを見ました。
チンカ・チンク系のトリックの途中にさらっと使われると魔法になるアイディアですけど、どんだけ前からあるんでしょうね、これ。
表に出しづらい手法な気もします。
2枚のコイン(其のⅠ)
1枚のコインを分割する動作で2枚に増やし、1 to 10カウントをします。
2枚のコイン(其のⅡ)
左手に2枚のコインを握るが、右手から2枚とも現れます。
2つのコイン(其のⅢ)
左手に2枚のコインを握るが、両手から1枚ずつ現れます。
ここだけ「2つ」と表記が変わっていたけどそのままにしておいた。
2枚の手順で使われている技法は石田天海氏のドロップバニッシュで、在来のものよりも美しく効果的なはず!と書いてありました。
カードと、4つのコイン
4枚のカードと4枚のコインを使ったアセンブリ。
エキストラ1枚を使う手順。デックから4枚のカードを抜き出す時に一緒にロードしますが、他にも色々使えそうです。
イタリアのバニ・ボッシ氏なんかはコインをデックに4枚隠したままリフル・シャフルしてましたし、割と色々出来るんですねー
客のストップしたカード
1枚ずつ配って観客がSTOPをかけた場所のカードが選ばれたカード。
サイコロジカルな手法のストップカード。
テンポ・タイミング・セリフなんかがかなり細かに書かれているので気になる人はどぞ。
終わりの方に書かれている、この手法をもう少し安全に使うためのアイディアの方が、好きな人は多いかも知れません。
第2巻第5号
美人の条件(石田天海)
立ち振舞に関するコラム。
奇術の中のパントマイム(フロタ・マサトシ)
フロタ・マサトシ氏のコラム第7回。首の向きについて。
ムスターフアーの貯金箱(林 実)
口が2つ付いた貯金箱の中に、金貨10枚が並んで付いたベルトを入れて輪っか状にする。
「こうするとお金が出ていってもまた戻って来る、でも増えません」というようなことを言った後に、観客に出たコインを数えてもらうと枚数が倍に増える。
とても説明の難しい現象。
有名な原理を変わった使い方をして手品っぽくしているけども、手品的な見せ方でなく、でんじろう先生(科学実験の)みたいに不思議な原理の紹介って形で使うとかでも良いのかも?などと思ったり。
飛行するカード 其のⅠ(福島 弘毅)
デックを2つのパケットに分け、一方で選んだカードがもう一方のパケットの中に裏向きで現れる。
現在だと色々もっとクリーンな解決法あるなーとか思うものの、パームを使わないアクロスの資料として。
どう考えてもバーノン・トランスファーやジム・クレンツのムーブ(タマリッツ・パーペンディキュラーとかを使った箱に入れるあれ)を使った方がフェアだよなぁと。
飛行するカード 其のⅡ(福島 弘毅/フロタ・マサトシ)
10枚の適当なカードをひとまとめにしてデックの隙間を通過させると、間に観客のカードが裏向きで現れる。
アクロス現象の表現のひとつとして。
見えないカードを撮み出して、こっちにポーイ。という演出以外にも、サンドイッチ現象チックな見せ方もありなのかもしれないですね。
それならサンドイッチでいいじゃん、とか言われてると何も言い返せないけども。
飛行するカード 其のⅢ(フロタ・マサトシ)
観客が分けた場所のカードが、演者の持っているパケットの上から現れる。
超有名なトリックデックを使う。そのデックを使う時に演じる候補にでも。
第2巻第9号
奇術の中のパントマイム(フロタ・マサトシ)
フロタ・マサトシ氏のコラム第11回。演技中の「手」について。
バック・パームとカード・チェンジ(小野 正)
タイトル通りということで。
自分のカードは御自分で(厚川昌男)
トップのカードを観客にデックの中程へ挿し込んでもらうと、その下のカードが観客のカード。
レギュラーデックで行うカード・スタブ。
見た目は多分シンプル。ちょっと動きがわかんないとこあるけども。
松田道弘氏の『魅惑のトリックカード・マジック』の中に「アワサカ/テンカイのカード・スタッブ」というトリックが収録されていて、泡坂氏と天海氏のやり取りの経緯なんかが書かれていますけど、このトリックはその話よりも数年前みたいです。
この手の現象が好きだったのでしょうか。
エスケープ・マジック(ダブル・トリック)(フロタ・マサトシ)
観客とマジシャンが大きな袋に入り脱出を試みるが、観客は案の定脱出出来ずに失敗する・・・と見せかけて、中から別の人が出てくる。
広い場所と、複数人の協力(観客、司会、助手2名、最後に登場する人)が必要だったりと、演じるチャンスはそうそう無いだろうなと感じる手順。
広い場所で演じる機会がある人は何か参考になる部分がある・・・か・・・?無い気がする。
わざわざ実際に演じた会と場所を書いてる辺り、まぁ演る人おらんよなぁと。
第2巻第10号
奇術の中のパントマイム(フロタ・マサトシ)
フロタ・マサトシ氏のコラム第12回。表現や体の動きについて。
プロローグのミルクジョッキ(百崎 辰雄)
ペーパーコーンに牛乳を入れ、火を付けると牛乳ごとコーンが消えます。
特に語ることもなく、でもウケるのは間違いないと思います。
ただ、最近は火気の使用がどこも厳しくなっていて、大きなとこだと許可の申請が面倒ですよね。
片手のカード・プロダクション(5枚カードの左手)(小野 正)
左手からカードが次々と出現します。
手が小さい人向けのマニピュレーション用の技法。
現代だと、両手で使ってたりする人をよく見る気がします。
え、これが初出だったりしますか?
「魔法を推理する」から(フロタ・マサトシ)
種明かし問題について。いつの時代も言ってることは同じです。
終幕のテープ(フロタ・マサトシ)
発表会のフィナーレで上からテープとか降らすための装置。
手品道具でもなんでもない上に、寸法などを書き込む前に印刷してしまったのか、重要な情報が空欄になっているので使い物にならないかなと。