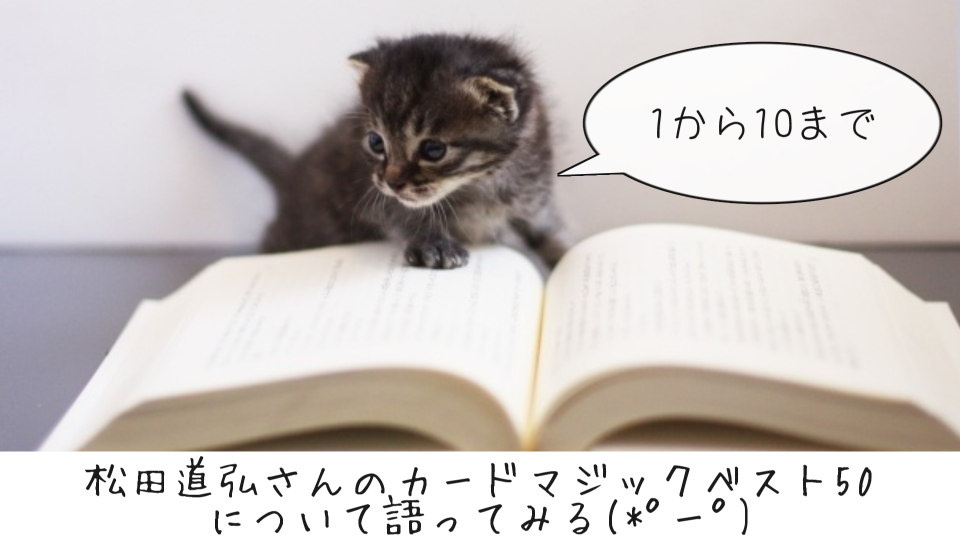手品を始めた頃ってそもそも、どういった手品があるのかも知らないもの。
とりあえずGoogleさんがおすすめしてくるものを確認するだけになってしまった昨今、あえて能動的に色々と調べようとする人の助けになるようなものがあったらええなーと思った次第。
で、わたし、松田道弘さんの『松田道弘のマニアック・カードマジック』に載っている「私の選んだベスト・カード・マジック・トリック 50」というコーナーに記載されている50のトリックを調べたりして手品覚えてたんですよね。
そのコーナーでは松田道弘さんが面白いと思った・歴史に影響を与えたと判断したトリック(またはプロット)が紹介されていて、ほんと先人が教えてくれるものは知っておくものだなと。
という感じで、刊行からもう30年も経ちますし、今見返したら色々と変わったものもあるだろうし、振り返りながら語ってみましょうかね。
1 Nu-way Out of This World
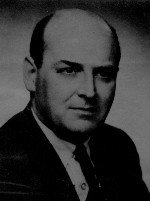 Paul Curry原案の「Out of This World」、これのUlysses Frederick Grantの即席バージョン。
Paul Curry原案の「Out of This World」、これのUlysses Frederick Grantの即席バージョン。
U.Fグラントのバージョンが原案から変わっているのは、演技時間が短縮され、事前のセットが不要になっているところ。
Nu Way Out Of This World by Ulysses Frederick Grant(Lybrary.com)
日本語になっているものだと「奇術入門シリーズ カードマジック」にU.Fグラントのバージョンが収録されていたりする。
たくさんのヴァリエーションが生まれたけど、元が完成されすぎているせいで、最後の部分くらいにしか差異が無いものがほとんど。もうお好みなのをどうぞって感じ。カードマジック事典やら大事典やら、大体の本に収録されてます。
個人的に押さえておきたいヴァリエーションはMichael WeberとDean Dillの「New World」、わたしが感心して今主に演じているのはBernardo Sedlacekが演じていたやつ(クローズドなレクチャーで教わったので公開されているかは知らない)。
New World by Michael Weber and Dean Dill(Vanishing inc.)
一応Out of This Worldの現象を書いておくと
トランプを裏向きに持ち、直感で2つの山に配って分けていく。
確認してみると、一方はすべて赤いカードで、もう一方はすべて黒いカード。
2 Eleven Card Trick
 Edward Victorのトリック。
Edward Victorのトリック。
シックス・カード・リピートの変形とも言われるトリックで、
11枚のカードを使ったトリックをしようとするが、数え直したり、観客に数えてもらったりしても、10枚になったり13枚になったりと、何故か11枚にならない。
という現象のトリック。
日本語で紹介してるものだと、松田道弘氏の『あそびの冒険 1巻』やカードマジック大事典、『デレック・ディングル カードマジック』に「DDの信じられないカードの飛行」(原題:The Derek Dingle Fabulous Jumping Card Trick)というヴァリエーションが載っています。
今類似の現象を挙げるとDavid Williamsonの「The Famous 3 Card Trick」が強いですね。こちらは枚数が11から3と減って、テンポがアップしています。
原案からの直接的な派生だと、Fred Kapsの「Fred Kaps’ Currency」を思い出しますね。
この手のトリックってお客さんからの反応は良いものの、演じてるとなんだかとても不安になるのはわたしだけでしょうかね。
スライト・オブ・デイブ 日本語字幕版(amazon)
Ridiculous by David Williamson(Vanishing inc.)
Seeing is Believing with Fred Kaps(Penguin Magic)
3 Aerodynamic Aces
 Bruce Cervonのインビジブル・パーム・エーセス。
Bruce Cervonのインビジブル・パーム・エーセス。
Larry JenningsではなくBruce Cervonの方を挙げているのは、パームが不要なところあたりが影響してるのであろうか?
Aerodynamic Acesはカードマジック事典で読めます(あれで理解できるかは甚だ疑問ではあるけど)。
Larry JenningsのOpen Travellers(Invisible palm aces)であれば、カードマジック大事典、ラリー・ジェニングスのカードマジック入門、ラリージェニングス カードマジックなど、割と日本語で読む手段は多いかな。
インビジブル・パーム・エーセス系統で個人的に好きなのは、JJ Sanvertの「Invisible Flush Palm」やHelder Guimarãesの「Aberto Court」。このあたりは推したい。
あ、現象は
左手に持った4枚のAが、1枚ずつテーブルに移動していく
みたいなトリックです。
The Best of JJ Sanvert Volumes 1 – 4 By JJ Sanvert(Vanishing inc.)
関連記事:「トラベラーズ」と「オープン・トラベラーズ」って違うの?
4 Oil and water
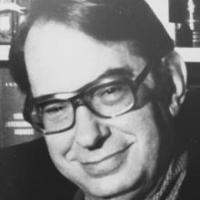 有名な「水と油」の中でも、ここではアスカニオの手順が挙げられている。
有名な「水と油」の中でも、ここではアスカニオの手順が挙げられている。
赤いカードを黒いカードを水と油に例え、交互に混ぜても分離する現象。
アスカニオの手順は、4枚4枚(+1)を2段行った後にエキストラを加え3段目を行う。
この手順自体は、アスカニオのマジック 2巻に収録されていて、松田氏の本でクレジットされているのは、アスカニオの本から理論やダブル・カードの扱いに関するものを集めて再編集したものみたいです。
同じスペインの流れを汲んでいるためか、Helder Guimarãesが『スモール・ミラクルズ』で演じているオイル・アンド・ウォーターの中にその動きが見れたりする。
記憶に残っているO&Wは、同じくHelder Guimarãesの「AN IMAGE TO START」。販売していたHP消えてるけど。
後は後年の色々な作品に影響を与えた、René Lavandの「It Can’t Be Done Any Slower」とかでしょうか。
Magic Of Ascanio – Studies Of Card Magic(Vanishing inc.)
Maestro by Rene Lavand(Vanishing inc.)
Mysteries Of My Life by Rene Lavand(Vanishing inc.)
5 Cards up the Sleeve
 手に持った10枚程度のカードが、1枚ずつ消えてポケットや肩口に移動するトリックのこと。
手に持った10枚程度のカードが、1枚ずつ消えてポケットや肩口に移動するトリックのこと。
松田氏が挙げているのはDr. Jacob DaleyとArturo de Ascanioのもの。
Dr. Jacob DaleyのCards up the Sleeveは、クラブのA~10までのカードを順にポケットへ飛ばしていくので、それに伴い裏で行う操作が少し複雑になっている。Ascanioの方は未読。
Cards up the Sleeveは比較的古い作品しか記憶に残っていなくて、Bill Maloneが演じていた「A Tribute to Johnny Carson!」くらいしか思い浮かばないです。あれはラストの意表をついた現象とテンポがとてもようござんした。
Stars Of Magic(Vanishing inc.)
Magic of Ascanio – More Studies of Card Magic by Arturo de Ascanio(Vanishing inc.)
Here I Go Again Volumes 1 – 3 By Bill Malone(Vanishing inc.)
6 The Card Under The Tablecloth
 文字通り観客のサインしたカードがテーブルクロスの下に移動するトリック。
文字通り観客のサインしたカードがテーブルクロスの下に移動するトリック。
松田氏はMatt Schulienと、Eugene Burger(改案)を挙げています。
わたしはEugene Burgerのヴァージョンしか見たことないですが、テーブルクロスの下にあるカードが見えるようになる瞬間がとても良いです。おしゃれ。テーブルクロスがいい感じの場所でしか演じれませんが、アンビシャス・カードなどの締めに演じてるととても綺麗にですわー。
The Magic of Matt Schulien by Philip Reed Willmarth(Lybrary.com)
7 Card Warp
現象がとても説明しづらい。しかし以前紹介したページがあるので説明はそちらに投げる!
関連記事:プロットCard Warp(カード・ワープ)
割と色々な本で大安売りされてるので簡単に調べられると思う。
原案でも十分だと思うけど、Howard Schwarzmanの「Star Warp」とか、Michael Closeの「Dr. Strangetrick」、1枚で行うDavid Jenkinsの「Warp One」、カードワープとしては変わり種なBill Goodwinの「Siamese Twins」、なんかが使いやすい手順かなと思います。
Warp One by David Jenkins(Vanishing inc.)
Siamese Twins by Bill Goodwin(Vanishing inc.)
関連記事:所感「シグネチャー・エフェクト by マイケル・クロース」
8 Cutting the Aces
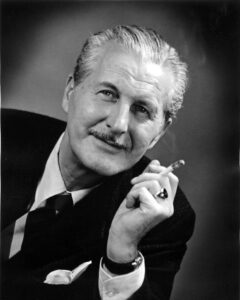 Dai Vernonのトリック。
Dai Vernonのトリック。
4枚のAをデックの中へバラバラに戻し、「片腕のギャンブラー」のストーリーに合わせて取り出していくというもの。
『Star of Magic』に収録され、日本でもカードマジック事典やら大事典やらに載ったのでよく知られている。
ただ、Star of Magicに収録されたのは「想定した読者層でも演じれるように簡単にしたもの」であり、日本語に訳されたものも、この簡単にした手順だけだったりする。
本来の「Cutting the Aces」を演じてるやつがいたら、確定でやばいやつだ。気を付けろ。
この手順は『Vernon Chronicles Volume 1: Lost Inner Secrets』で読むことが出来ます。
そういえばヴァーノン・リベレーションズの1巻(たしか)で、Michael AmmarがCutting the Acesを演じていたんだけど、動きのたびにVernonが「違う、そうじゃない」と、ダメ出しをしていたなぁと思いだしたり。
*見返したら、AmmarじゃなくてSteve Freemanが駄目だしされてました。
Vernon Chronicles Volume 1: Lost Inner Secrets (eBook)(Vanishing inc.)
Stars Of Magic(Vanishing inc.)
9 Cannibal Card
Fred Kapsが来日した際に見せてもらったCannibal Cardが挙げられ、『松田道弘のマニアック・カードマジック』にその解説がある。
松田氏がFred Kapsの手順を見た後、Michael Ammarの『Easy to Master Card Miracles Volume 1』にCannibal Cardが収録されていると聞いて購入し視聴したが、ほぼFred Kapsと同じ手順だけど比較対象がFred Kapsだと、さすがに見劣りするというようなことを書いていました。
Cannibal Cardは松田氏を始め、色々な人が多数の改案を出していますが、総合的に原案を超えたと感じるは今のところないかなぁと。
Guy Hollingworthの「Cannibal Cards」、Mago Migueの「Cannibals」でしていたアプローチの仕方なんかは興味深いなと思いましたが。あとはショーのために盛りに盛ったJosé Carrollの「Cannibals!」などでしょうか。
クレジット周りについては色々と複雑なので、興味のある人は石田隆信氏のコラムを読んでもろて。
石田コラム:第44回 カニバルカードの歴史と謎
石田コラム:第119回 フレッド・カップスのマジック
Allegro by Mago Migue(Vanishing inc.)
52 Lovers by José Carroll(日本語版)(緑の蔵書票)
Guy Hollingworth『Drawing Room Deceptions』(日本語版)(教授の物販)
関連記事:所感「ロンドン・コレクション by ガイ・ホリングワース」
10 Chameleon Card
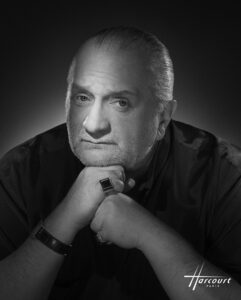 Dominique Duvivierのディーラーズ・アイテム(売りネタ)。
Dominique Duvivierのディーラーズ・アイテム(売りネタ)。
カードのフェイスに、近づけたものが印刷されていく、ユニバーサル・カード現象のような、ワイルド・カード現象のような、そんなトリック。
今でも入手可能だけどアップデートされて、表記はないけど「バージョン2.0」的なものが売られています。正直昔見た古いバージョンのほうが良かったような気がしないでもない。
Joshua Jayの『Close up. Up Close vol.2』の中で、実演のみですが Dominique DuvivierのChameleon CardのJoshua Jayヴァージョンが演じられていました(題名はprinting)。
The Chameleon Card by Dominique Duvivier(Vanishing inc.)
Close up. Up Close Joshua Jay(Vanishing inc.)
とりあえずベスト50のうち10までを。続きは反響があったら書くかもしれない。