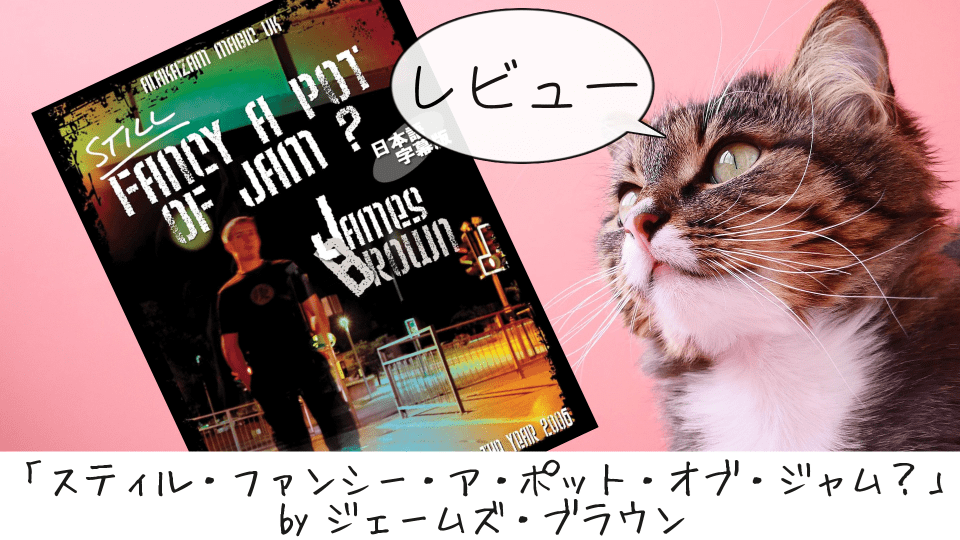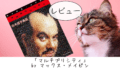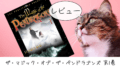- Still Fancy A Pot of Jam? by James Brownとは?
- 総評的な
- 個別に所感
- Card Opener(カード・オープナー)
- Psychological Deck Vanish(サイコロジカル・デック・バニッシュ)
- 11p Trick With Pot of Jam(11ペンス・トリック・ウィズ・ジャム)
- Card Under Watch(カード・アンダー・ウォッチ)
- Card Under Box(カード・アンダー・ボックス)
- Diminishing Switch(ディミニッシング・スイッチ)
- Coin Under Watch & Watch Steal(コイン・アンダー・ウォッチ&ウォッチ・スチール)
- Band Up!(バンド・アップ!)
- Spectators Card To Envelope(スペクターズ・カード・トゥ・エンベロープ)
- Brainless Travellers(ブレインレス・トラベラーズ)
- Mercury Card Fold
- Convincing Control Palm
- Chav Magic
- Card To Spectators Pocket
Still Fancy A Pot of Jam? by James Brownとは?
スクリプト・マヌーヴァから日本語字幕が出ているJames Brown(ジェームズ・ブラウン)氏のDVD作品集。
氏は2006年のマジック・サークルでクロースアップ・マジシャン・オブ・ザ・イヤーに輝いたりしたことがある実力派。
この作品以外にも、DVD『Hide&Seek』やDVD『Professional Opportunist』シリーズなどもリリースしているようである。
*動画は英語版
スティル・ファンシー・ア・ポット・オブ・ジャム? ジェームズ・ブラウン(スクリプト・マヌーヴァ)
Professional Opportunist Volume 1 by James Brown(Vanishing inc.)
Hide & Seek by James Brown(Vanishing inc.)
総評的な
雑だな。というのが率直な感想。演技も解説も。
ミスディレクションやオフビートを多用した手順が多いが、ミスディレクションやオフビートについてきちんと説明されているかと言えばそうでもない。
なんかためになること言ってたっけ・・・?言ってないね。
また、トップチェンジやらパームやらサイドスチールやらカウントやらは「ここでトップチェンジします」と口頭一言で済ませるので、やり方を知らない人は辛いだろう。
収録されているトリック自体は悪くないけど、そのまま演じるにはちょっと良くないのに、観た人が自分で考えれるようなアドバイスも大したことないのでうーん。
すでにある程度技法を習得しており、ミスディレクションもオフビートも使いこなせてる中級者くらいの人が「こういうのもあるで」ということを知るために観る。くらいが丁度いいのでないだろうか。
あと「ミスディレクションやオフビートを使っているから、雑にやっても観客にはバレない」と豪語するプロの方をたまに見かけるのだが、雑にやってるのを傍から見たときどれだけ無様か客観的に見れる資料としては良いかもしれない。
技法やらそういうのは完璧にやった上で、適宜ミスディレクションやオフビートで補強するのが理想なんじゃないかい?ラムゼイさんが泣いてるぞ?
と、そんな感じですかね。ネタが欲しい中級者向けじゃないかな?初心者向けの教材にはならないかと。
個別に所感
Card Opener(カード・オープナー)
取り出した関係のないカードが観客のカードに変化したり、ポケットに移動したり、デックが消えた1枚だけになったりする。
氏がちょっと見せるときに演じているオープナー。
目を引くプロダクション、チェンジ、カード・トゥ・ポケット、デック・バニッシュがテンポよく立て続けに起きるのでオープナーにはちょうど良い。
実演時、見えてはいけない操作がもろに映っているので、観賞用には向かないがマジシャンが動きを参考にしたいときはいいかもしれない。
Psychological Deck Vanish(サイコロジカル・デック・バニッシュ)
観客の選んだカードを残してデックが消える。
ラリー・ジェニングスの2枚で行っていたトリックを1枚だけで出来るようにしたやつ。
立ってても座ってても観客が一人でも大勢でも演じれるトリック、ということだが状況によっては演じないほうが良いトリックなんじゃないかな。
舞台俳優でもそんな動きしないよ、みたいなジェスチャーがわざとらしすぎる。確かにバレんかもしれないが好きじゃない。
座った状態や、立った状態でも少人数の観客相手なら綺麗に演じれるだろうし悪いトリックではない。
ただ、どちらかといえばジェニングスの原案の方が好き。状況次第ではこっちをやる、とかがいいんじゃないかな。
11p Trick With Pot of Jam(11ペンス・トリック・ウィズ・ジャム)
10ペンス硬貨と1ペニー硬貨の合計11ペンスを手に握り、10ペンスを抜き取るが手には11ペンスある。今度は1ペニーを抜き取るがやはり11ペンスある。さらに10ペンスを抜き取ると今度はジャムの瓶が出現し、その後に瓶が消える。
このDVDのタイトルの由来はここで語られます。
古典トリックのクライマックスで出す物を変えて、消失も行うようにしたあたりが改案したとこなのだろうか?
日本円でも演技可能。
わたしはマジックショップ「フレンチ・ドロップ」店長の武宮将氏のレクチャーに参加した際に習ったように510円で演じてます。

そういやカメラが引きすぎて、元ネタ知らないと解説で言ってること理解しづらい気がする
最後にジャムを取り出す意味がなんというか、心底どうでもよかったので(「ジャムの人」みたいに認知されたとか、その後の現象で使うとかならまだ納得いったんですけど)、出す物はちょっと考えておきたい。
本来出す予定のものが使えなくなって、その場にあった代用品出したらウケたとか。その先の話を期待してたのに残念である。
また、消失の部分に関してはオフビートで誤魔化すだけなのでなんていうか、どうでもいいです、はい。
と、色々思うことはあったがトリック自体は原案がそもそも素晴らしいのでおすすめではありんす。
Card Under Watch(カード・アンダー・ウォッチ)
観客の選んだカードが観客の時計の下に挟まっている。
古典だが従来のものとは考え方と違うと言っているが、何が違うのがちゃんと話して欲しい。
何一つ違いが分かりません。

もしかしてタイム・ミスディレクションのくだり・・・?従来からそうじゃね?
類型のトリックを演じてる人は演出というか、観客の時計に意識を持っていかせる流れが参考に出来ると思います。
正直あんまり上手くないと思った。
Card Under Box(カード・アンダー・ボックス)
観客の選んだカードやデックが、いつの間にか箱の下に移動している。
観客にはカードを2枚選んでもらうことになる手順。
有名なギミックである「バニシング・デック」を使って最後に2枚を残してデックが完全に消えるというバージョンも解説されている。
まぁ参考になると思う。ちょっとわざとらしい動きが多いのであまり好みではないが。
Diminishing Switch(ディミニッシング・スイッチ)
観客の手の上にミステリー・カードを1枚置いておく。
観客に1枚カードを覚えてもらった後、4枚のカードをヒントとして抜き出すがその4枚すべて観客のカードに見えるが、次の瞬間には4枚のキングに変化。観客の手の上にあった1枚のカードを見ると4枚のキングになっており、マジシャンは手に観客のカード1枚だけを持っている。
現象を書くと意味が分からない。
が、観客から見ると意外に分かりやすいらしいトリック。
観客の手に置いたカードにほにゃららするために、無駄に観客と接触しようとするのがあまり好みではない。
観客の手の上で現象を起こすのが効果的なのは分かるが、ちょっと多すぎなんじゃないかね。
とはいえトリック自体は優秀だと思います。
類似のトリックだとヘルダー・ギマレス氏の「ヘルダー・スケルター」やゆうきとも氏の「ワイルド・ワイフ」とかがありますね。
所感:「RED MIRROR by Helder Guimarães」レッド・ミラー by ヘルダー・ギマレス
Coin Under Watch & Watch Steal(コイン・アンダー・ウォッチ&ウォッチ・スチール)
コインが観客の時計の下に移動。
腕時計をスリ盗る。
解説は最低限である。
注意点とかもっと色々あるだろうに。すでに知ってる人が見て得るような情報はないかと。
スチールも同様。
革バンドは比較的壊れやすく、日常的に使用する上で結構気を使うものだが、バンドに対してやってはいけないことを観客の時計で行うので、まともな感覚の人であればやらんほうが良いと思いますけどな。
腕時計を一目見て値段が分かる、少し話してその人が物にどの程度思い入れを持つ人か察せない程度のマジシャンならやらんほうが良いと思いますよ。
ウケるのにこのマジックをやらない意味が分からないという発言がありましたが(これはカード・アンダー・ウォッチのとこでですね)、わたしは一人称視点の意見だけでそう断言出来る神経の方が分かりませんねぇ・・・。
やるなじゃなくて、やるならもっと頭を使え。と言いたいだけですからあしからず。
Band Up!(バンド・アップ!)
デックに輪ゴムをかけて観客の手に近づけると、観客のカードだけが輪ゴムで手の甲にぱしっと出る。
古典的なトリックを観客の手の甲で行えるようにした作品。
印象に残る良いトリック。原案を知らなければここで覚えておくと良いと思う。
使用する輪ゴムのサイズについても言及してるのでちゃんと聞くように。
日本で一般的な輪ゴムだと、きっと痛い。
Spectators Card To Envelope(スペクターズ・カード・トゥ・エンベロープ)
1枚のカードの裏に観客がサインし、さらに1枚のカードの表にマジシャンがサインする。
封筒の中のカードの裏と表に観客とマジシャンのサインがしてある。
グダグダ過ぎるんじゃないかな?
観客がマジシャンに見せるトリック、というテーマらしいが観客が困っているしマジシャンの段取りも悪い。
クライマックスのために他のすべてを犠牲にしたみたいな。
原案に謝ってほしい。終わりが良くても許せないものはあるんだなと思った。
Brainless Travellers(ブレインレス・トラベラーズ)
10枚ずつのパケットを2つ作り、観客の覚えたカードがもう一方のパケットへ移動する。
多分このDVDの目玉で、なんかスタンダードになってしまった感のあるカード・アクロス。
このトリックの根幹をなす例のムーブは、パケット・トリックのようなシャドウ・ゾーンの狭い状況下では胡散臭いことこの上ないですが、サロンやパーラーのようなシャドウ・ゾーンが広くなりがちな状況では有効だなと感じました。
覚えておくと重宝すると思います。
Mercury Card Fold
普通のマーキュリー・ホールドの解説。
ここから本編ではなくて特典映像的なもの。
有用なフォールドにどんなのがあったかな?と考えてみると、マヌエル・ムエルテ氏のフォールド(この記事見返したら書いてあったけど、どれのことがわかんね)や、シン・リム氏のフォールド、G氏の「V2F」がパッと出ますね。
なんだかんでオーソドックスなやつが便利過ぎて、変わったやり方が定着しにくいなぁ。
所感:「At the Table Live Lecture Vol.3 – (AUGUST2014) – Shin Lim」
V2F 2.0 by G and SM Productionz(Vanishing inc.)
At the Table Live Lecture Shin Lim(Penguin magic)
Convincing Control Palm
コンビンシング・コントロールから左手にパームする技法。
角度に非常に強くフラッシュしにくいのが利点ですかね。
Chav Magic
若いガラの悪そうな少年たちにカード・マジックします。
Chav って何かと思って調べたら蔑称じゃねぇか。
チャヴ(Chav)とはイギリスで使われている言葉で、スポーツウェアを着た反社会的な若者についてのステレオタイプをあらわした蔑称である。
Wikipediaより引用
カード・アンダー・灰皿やカード・チェンジ、アンビシャス・カードなど。アドリブで色々やっているように見えます。
飲み屋のようなフリーな場で演じるときの参考にどうぞ。
Card To Spectators Pocket
観客のカードが観客のポケットへ移動する。
3段構成になっている。
ストリートやマジシャンの左右に観客が座っているような状況に適してそうなマジック。
1800年代から1900年代初期辺りに流行ったやーつとか思ってる。
上手く行けばめっちゃ観客の印象に残る。