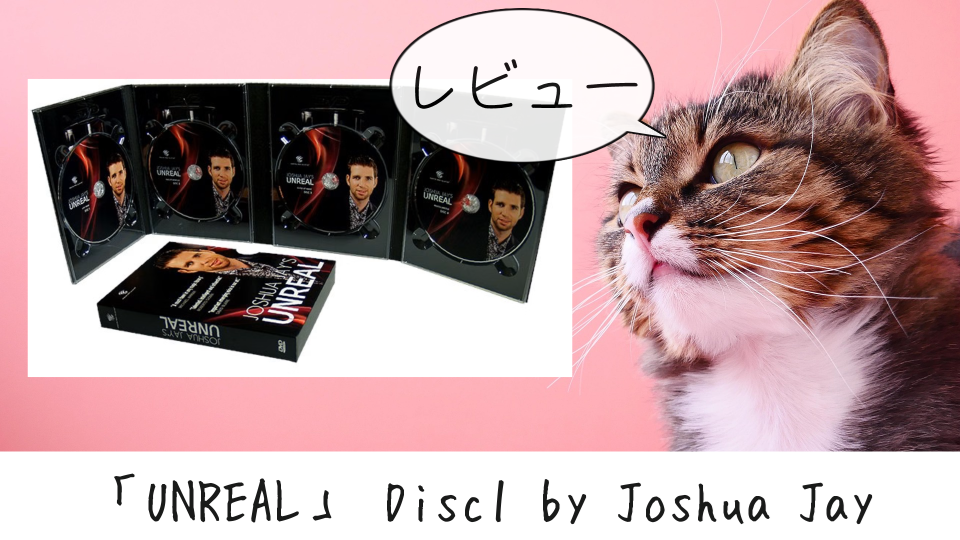EMCから出ているジョシュア・ジェイの4枚組DVD。タイトルは氏のマジックシアターショーのタイトルから。Disc1のレビューっぽいの。
ポルトガルのコインブラで行われたマジック・シアター・ショー「UNREAL」をフル収録。収録時間は1時間ほどで、ネタ数的には8個くらい。
ソロでここまでのショーをする機会のある人は中々居ないと思うが参考になります。

この記事、fantiaに数年前に載せた記事なんだけど、自分で調べなおすときにfantiaだと面倒すぎるのでこっちに持ってきた次第
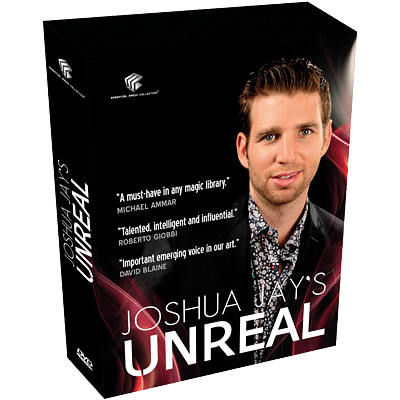
Disc2のレビュー
Disc3のレビュー
Disc4のレビュー
song prediction
観客が自由に選んだ曲を、映像の中の人が当てる。
ジョシュアと録画映像のコントから予言にいく手順。
スタッフによるプレショー・ワークが必要なので、余程大きい規模のショーをやるとかでもないと演じる機会はない。
プレショーを失敗したときの保険をかけているのと、実際に失敗したときの話をしているのでその辺りは知ってて損はないかな。こういう心構えは嫌いではない。
めっちゃ良いリカバリーとは言えないけど、完全に失敗するよりはマシかと。プレショーを必要とする大舞台だからこそ出来るリカバリー。
reverse logic
デックを混ぜる、カードを選ぶ、カードを見つける、拍手。の一般的なカードマジックの流れを逆順に演じる。
割りと色々なことがあるので詳細は割愛。使用する小道具(ギミック含む)もかなり多い。
ギミックに+αで保険かけた工夫を施しているんだけど、こういう心構えは好き(2回目)。
How I Evolved Reverse Logic(リバースロジックを進化させた方法)(vanishing inc.)
Reverse Logic by Joshua Jay(Vanishing inc.)
hitchcock
1枚のカードを4つに破いて置いておき、4人の観客に対してカード当てを行う。
4人の観客のカードがいつの間にか1/4ずつ破れており、最初に破いた破片が観客のカードの敗れた破片になっている。
一度準備してしまえば、演技の度に破るカードは1枚で済む。
演技後はデックがレギュラー状態になるので続けて色々演じれるが、大体の状況だとクライマックスの演目だよなー。
bill in lemon
グラスの中にレモンが出現する
タイトル詐欺。ビル・イン・レモンを演じる前に出来るかっこいいレモンの出現である。
演じてる手順は普通の手順だから、あとは好きなビル・イン・レモンを演じてくれ。だそうだ。
グラスとハンカチでレモンをかっこよく取り出したいのなら良いと思う。
any card at any page
観客の選んだカードが、観客の選んだ数字のページから出現する。
多分、北原風にいうとネゴシエーションの領域。
この手順をそのまま演じないにしても、カードを選んでもらった後に行っているサトルティの数々は参考になる。フォーシングデックを使うときのね。
また、フォースを失敗したときの話とかがいい感じで、デックのトップとかボトムから取られたら?っていう質問に対するわかりやすい答えを提示してる。
実演時でもフォースを失敗しリカバリーしており、トム・マリカのエピソードも話していたりするので聞いておけばいいと思うよ。
ちなみにこのトリックは、色々な作品集で登場してるけど、目次がローマ数字で本編が数字でページ表記されてる本が良いってアドバイスは初めて聞いた気がする。セットの場所が偏るなーってずっと思ってました。
どのサイズの本までだったら問題なく機能するのか検証したいところだよね。
bandage routine
左手に包帯を巻いた状態で行う、日用品の場所の予言と包帯を巻いた腕に移動する腕時計の手順。
そのまま演じることは絶対にないと思うけど、構成してる色々なアイディアは参考になると思う。グラスの中に入れた物を消す方法とか、スケッチの予言とか、腕時計のサトルティとか。
包帯を巻くときにしている話は実話で、Disc2で詳しくその時について話してました。
around the world
10枚ほどのカードを観客に覚えてもらい、世界中のいろいろな地域にちなんだりして次々と当てていく。
クライマックスで使っている特注のカードフレームについてはノーコメントで。入手できないものなんぞ知らん。
観客に10枚引いてもらった後、観客にデックを渡してカードを戻してもらい、混ぜてもらうまでを自由に行ってもらった後に返却、そこから次々当てていくフェイズに入れるのはとても便利なアイディア。
ムービングピプスみたいなギミックを割りと無理なく連続で組み込めるので、眠っているギミックカードをこれでもかと連続使用出来るかもしれません。
ちなみに10枚という枚数に縛りはないが、そのくらいの枚数が一番自然な状況として観客に認知出来るだろうとかそんなん。わたしもそう思う。
複数枚のカードを次々当てるというコンセプトだと、ジョン・ガスタフェローの「Multi-Mental」を思い出すんだけど、あっちがカジュアル寄りだとしたら、こっちは最後だから全力でぶん殴りに行く用って感じかなぁ。同じコンセプトなのに手法とか重要視してる部分が違うの面白いですね。