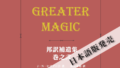トランプマジックをする上で、未だに(2025年時点)おすすめの入門書のひとつとして挙げられる『Expert Card Technique』のPart4-Chapter2、カード当てを集めたチャプターをすべて読んだのでその感想を。
前回の→『Expert Card Technique』のPart4-Chapter3を読んだ感想まとめ
Fantia・Creatiaにすでに投稿した記事から、ちょっと都合の悪い部分はカットしてまとめました。
翻訳したものはこちらに公開してあります(サブスク登録者限定です)
Fantia
Creatia
The Zingone Spread
記載はないけど、後世のマジシャンたちの情報によるとLuis Zingoneという人のトリック。
Merlin spreadというトリックの、Luis Zingoneバージョンだからそういう命名なんでしょう。
現象は
スプレッドしたカードの中から、3人の観客にそれぞれ1枚ずつ、計3枚のカードを覚えてもらい、スプレッドしたままのデックへバラバラの位置に戻してもらい、カードを綺麗に揃えてもらう。マジシャンはポケットから3枚のカードを取り出してテーブルに置くと、それが観客の覚えたカードである。
というもの。
普通に不思議である。
原案?(Merlin Spread)ではキーカードやクリンプを使っていたとのことだけど、このトリックはそういった策略は用いずに、観客にデックをシャッフルしてもらい、そのままテーブルにリボン・スプレッドして開始できる。
マジシャンがデックを持って行えば簡単に色々な方法で出来るだろうけど、それが出来ないようにリボン・スプレッドからの観客に揃えてもらうである。まぁその後にデックは持つけども。
さらっと出来たらとてもカッコイイと思うんだ、この手のトリックは。
The Gamblers Outwitted
Paul Rosiniがサンフランシスコで残した伝説と、そのときに演じたトリックの解説。
現象としてはいわゆるImpossible location。
私はこれを読んで、Mark Calabreseの「DVS」っていう作品集のPVを思い出しました。イメージはまんまPVの中で演じてる最初のトリックですわ。
原理的にもPaul Rosiniのトリックの発展型といえますし。ちなみにと言いますか、この時代Paul Rosiniが演じたトリックの原理自体は、ギャンブルに携わるものであれば誰でも知っているはずのもので、それをディーラー相手にやって騙しきったってことで、ようは演じ方次第なんだよニヤリって感じです。
かっこええですね。
DVSのPVを貼っておくので、良かったら見てくだされ。ちょこちょこ名前出しているんですけど、ここ20年出た中で一番カッコイイ手品PVだと思ってます。

逸話はカットした
A Rosi-Crucian Mystery
2段構成のカード当て。インポッシブル・ロケーション。
前回の「The Gamblers Outwitted」と同じくPaul Rosini氏のトリック。同じ原理も使っています。
一段目では観客がシャッフルしたデックで「The Gamblers Outwitted」と同じ原理を使ってカードを当て、その最中に秘密裏にデックをセット、二段目ではそのセットを使ってカードを当てます。一段目と二段目で相互に観客の推測をキャンセルアウトしてます。
まぁ一段目は不思議だけども使いにくい原理ですが、二段目・・・というか一段目の最中なんだろうけど、演技しながらのセットはダニ・ダオルティス氏やジョン・ガスタフェロー氏あたりがよう使ってるようなイメージがありますが、とても便利で有用なアイディアだと思います。このトリックでの説明は割と雑ですけどもね。
Two—Six—Four
現象
観客に1枚のカードを見て覚えてもらった後、デックを2つに分けて出てきたカードの数値を合計し、その分の枚数を配ると覚えてもらったカードが出てくる。
ダイ・バーノンのトリック。
このときが初出っぽい。この後バーノンの作品として有名な著書に出てきたっけ?となったけど、調べたら割と出てきてた。全然知らなかった。
マルチプルアウト系や、説明できないトリックなんかが磨かれていく最中の作品なのでしょうか。観客に「覚えたカードのあった枚数目」を覚えてもらうっていう、とてもやりたくない操作が入っていて(そして現象の説明から省いた)、解説中でも触れてたけど何度も繰り返せるようなトリックではない。というような弱点もある。でも、トリックが始まる前置きの部分で必要なセットを組んでしまう、っていうアイディアはとても面白いなと。
色々なトリックに組み込めないものかなぁ~。
The Mind Mirror
Jack McMillenの二段構成になっているインポッシブル・ロケーション。
Paul Rosiniの「A Rosi-crucian mystery」と現象は似た感じだけど、Rosiniが「即席で一段目」→「秘密裏にセットして二段目」で、McMillenは「セットを使って一段目」→「秘密裏にセットして二段目」という感じ。
Rosiniは相互に補完する印象だったけど、McMillenは「リクエストされたら繰り返せる」ほぼほぼ観客の見た目は同じにした感じでしょうかね。
現代でもこの原理を個別に使う人はたまに見かけますが、McMillenは双方を上手く組み合わせていると思います。
Predestined Choice
現象はレギュラーデックでやるブレインウェーブ・デック。
考案はCharles Miller氏。赤デックと青デックを1個ずつ使うので、普通に1デックで演じているときに使い所はないと思うけど、2デック使ってDo as I doとかを演じているのであれば覚えておくと使い所がありそう。
この手順の前段階で色々することでこっそりと準備を行い、観客にどちらかデックを選んでもらって、そのデックでブレインウェーブ・デック現象を演じます。
似た構成(このトリックの開始時点のカードの配置)のトリックは、カラーチェンジングデックで見かけたりしますけど、現代だとカードケースにまんまセットして入れておいてオープナーで演じておしまい、あとはレギュラーで出来るトリックを続ける。ってのが多い気がします。
ただこのトリックは、別のトリックを利用して準備するっていう策略を用いている都合上、オープナーには使えず、中間かクライマックスにそれまで使っていたデックでブレインウェーブ・デックをするっていう構成が、とても面白いと感じました。
「オープナーには使えず」ってめっちゃ書いたけど、諸々のサトルティが無駄になるからこのトリックをオープナーに選ぶとかセンスない、みたいな意味です、すまそ。
Reading the Cards of any Deck
Jean Hugard氏のトリック(Lybrary.comにある、考案者を足した目次によると)。
現象は、観客に混ぜてもらったデックを背中に回し、指先だけで一番上のあるカードの表面を読み取って当てていく。というもの。
この手のトリックだと、アンネマンの「The Mystery Card Reading Method」(『The Book Without a Name』収録)が、最近読んだということとその実用性からとても印象に残っているけど、この方法も中々に便利。個人的に大きいのはデフィニットなクライマックスを付加しているところ。
アンネマンの手順のように、ス・・・と終わるのも悪くはないけれど、クライマックスに出来る現象がついてるととても使いやすい。
通常の読み取る部分は、わたしとしてはアンネマンの方が好みだけど、それぞれ一長一短あるのでお好きな方をってところ。
アンネマンの手順は、一度手順を開始したら読み取れる回数が決まっているが、デックのボトムが固定なので動いてフラッシュしても問題ないあたりが便利。
ヒューガードの手順は、観客のリクエストに応じて読み取りは自由だけど、デックのボトムを見せるのが絶対NGなので、動いてフラッシュしてしまうようなことは絶対に避けないといけないところが気を使う部分。
フェアさだとアンネマン、楽さだとヒューガード、という感じかな。誤差だと思うけど。
個人的にはアンネマンの手順をやって、クライマックスだけヒューガードさんって感じが良さそうだなと。
【紹介】The Book Without a Name by ANNEMANN
Dexterous Fingers
現象を一言でいうと、観客の言った枚数を即座に取り上げるというもの。状況に応じて現象を増やすことも可能だけど、基本は3段になっていて、1,2段目は観客の言った枚数を即座に取り上げ(1段目は少なめ、2段目は1段目よりも10枚くらい多く)、3段目は観客のカットして取った枚数を言い当てるというような感じ。
このトリックの数年前にBilly O’Connorという人がカードの枚数を当てるトリックを発表したけど、それではギミックカードを使っていたようで、Charles Millerがそのトリックをベースにして考案したトリックだそうで、レギュラーで即席で演技可能。
現代でも問題なく演じれるレベル。同じプロットの作品も数多くあるだろうけど、構成としてはピット・ハートリングのFinger Flickerが近いかなーという印象。Card Fictionsに先行作品として書いてあったっけー?と思ったけど一言も出てこないね、うん。